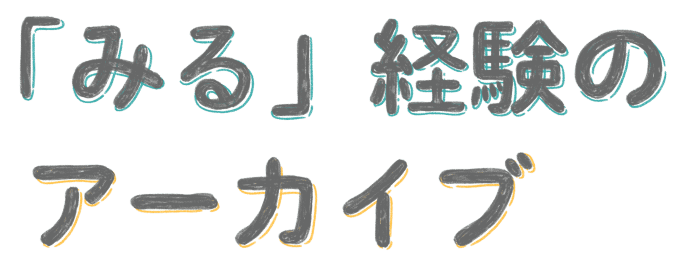【ダイジェスト記事】オンラインイベント「『みる』経験のアーカイブを読む」

2012年に活動を始め、今年で12年目を迎えた視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ。これまでの活動をまとめたアーカイブサイト「『みる』経験のアーカイブ」に掲載された記事からピックアップした内容をもとに、当団体のスタッフと、三重県立美術館のエデュケーターである鈴村麻里子さんと一緒に語り合うイベントを、去年12月20日に開催しました。
アーカイブは、活用する人や読む人によって様々な意味を持ち得るもの。記録として定量的データを残すこともありますが、一方で物事をわかりやすく単純化することで、見えなくなってしまうものもあります。現実世界にはもっと複雑なことがたくさんあって、それは例えば人数という数字の中には決して現れません。
そんな、「複雑なもの」を複雑なままにアーカイブしたいという方向性をもって始めた「語りのアーカイブ」。そこに掲載された3つのインタビュー記事の中に、それぞれの言葉で表現されたニュアンスや、感じていたけれど言葉にできなかった「何か」を、再度さまざまな立場の人と読んで語ったのがこのイベントです。この記事では、そこでみえてきた共通点や、共有されたモヤモヤのダイジェストをお伝えします。
対象記事へのリンク
参加者プロフィール
鈴村麻里子
三重県立美術館学芸員。
愛知県生まれ。2011年から現職。専門は美術館教育とフランス近代美術史。近年は美術館のアクセシビリティに関わる事業を担当。簡単には言語化できない作品に、何度も向き合うことが楽しみ。
林建太
視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップスタッフ。
1973年東京生まれ。鑑賞ワークショップでは主にナビゲータを務めている。美術や映画が好きで、そのことを語る会話の不思議さにも興味がある。
中川美枝子
1994年埼玉生まれ。全盲の視覚障害当事者。7年前にワークショップと出会って以降ナビゲーターとして活動。現在は埼玉県内で英語の教員として勤務。大学で文学研究を専攻していた経験から、ワークショップで飛び交う言葉とその背景にあるものを分析するのが好き。
衛藤宏章
視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップスタッフ。
1987年生まれ、大分県別府市在住。23歳の時失明、現在は全盲。アートに興味を持ったのは見えなくなってから。作品を鑑賞する人を鑑賞するのがおもしろい。
活動と語りのアーカイブ
今回のトークイベントは、団体のスタッフの3人に加え、三重県立美術館のエデュケーターの鈴村麻里子さんをお招きし、スタッフ内だけではなく外側の視点からのコメントを頂きながら、話を進めました。
鈴村さんは、アクセシビリティを大きくテーマに据えながら、一人ひとりの来館者の経験が意識された展覧会をされています。鈴村さんをお呼びしたのは「テーマの内側だけではなく常に外側を見ている方」だから、という林さん。アクセシビリティは、当団体も常に意識しているテーマです。しかし、それをテーマに揚げたとたんに、そこに集まるさまざまな人の経験が「アクセスできたかどうか」という結果や数字に集約されてしまうことも少なくありません。このイベントでは、そんなちょっとモヤモヤするようなプロセスのことも含め、テーマを固めずに自由に話していくことにしました。
林
今回は、新しく公開した「語りのアーカイブ」より3つの記事を軸に話していきたいと思っています。鈴村さんには事前に記事を読んでいただいたのですが、まずご感想はいかがでしたか?
鈴村
そうですね。アーカイブサイトに関してですが、私も普段自分が美術館のスタッフとして、ワークショップを何回開催して、それに何人参加したのかというような定量的な記録を作りがちだったので、そこでこぼれていくものがとてもたくさんあるということを感じていました。今回立ち上げてくださったウェブサイトのように、二つの「活動のアーカイブ」と「語りのアーカイブ」という、同じ経験に基づいているけれど方向性が違う2つの軸をつくられたというのが、すごく面白いなと思って拝見していました。
林
ありがとうございます。そうなんですよね。サイトは2軸になっていて「活動のアーカイブ」は人が集まる「場」を主催者の立場からみた記録で、「語りのアーカイブ」は場に集まった「人」の個人的な視点から語られた記録です。その「語りのアーカイブ」の記事から、鈴村さんに気になる部分をピックアップして頂いたので、その鈴村さんのご感想や視点を起点にして、中川さん、衛藤さんまたは僕なりがどう見たかという話や、どこが面白かったかを話すというようにすすめましょうか。

「自分の脳がいろんな編集パターンになって、粘土をこねるようにイメージを作っていく。鑑賞が楽しいと感じるのは、それがクリエイティブだから」(岡野宏治さん)
「私の頭の中でポンと押したハンコが、他の誰かの言葉で打ち消されて、最初のハンコを上書きしていく。それが楽しいのかもしれないです」(大沢郁恵さん)
私たちの美術鑑賞ワークショップに参加された、見えない参加者の大沢郁恵さんと、岡野宏治さんへのインタビュー記事。それぞれ異なる言葉で語られた「みる経験」ですが、お二人のお話を通していくつか共通点が浮かび上がってきました。キーワードは「つくる」ということと「クリエイティビティ」。
「みる」ことがおもしろい時、そこには創造性という要素が根底にあるようです。
鈴村
「語りのアーカイブ」の記事に登場する岡野さんと大沢さんですが、それぞれにご自分の言葉で鑑賞のことを語っていらっしゃったのがすごく印象的でした。具体的には、岡野さんが「編集」という言葉で、そして大沢さんは「スタンプをポンポンと押していくような体験」という表現をされていますね。
中川
そうですね。私も、岡野さんと大沢さんの記事を拝見したときに、やっぱり今鈴村さんがおっしゃったところが、どちらも印象に残っていて、編集者とかスタンプというところはとても面白い。お二人の表現を聞いて、すごく頷きながら読んでいました。
鈴村
そうなんですよね。まずは岡野さんのインタビューから印象的だった部分を引用しますね。
林
はい、お願いします。
鈴村
「(複数人で見る作品鑑賞において)正解にたどり着くというよりは、色々な情報から自分でつくっていく。自分の脳がいろんな編集パターンになって、粘土をこねるみたいにつくっていく。だから、(鑑賞が)楽しいって感じるのは、そこがクリエイティブだからだと思うんですよ」という話があるんですよね。
中川
「編集」というところもそうですが、「クリエイティブ」という部分も、すごく共感しました。岡野さんが、自分の頭の中で、粘土をこねて作るようにだんだんイメージがわき上がってくるとか、誰かが用意した情報をポンッと与えられるのではなくて、鑑賞って自分で立ち上げていく経験だから楽しい、というお話もされていて。それを読んで、いろいろな人の言葉があって、みんなでつくり上げてくからこそ出てくる体験というか、湧き上がってくる経験なんだと再認識しましたね。
衛藤
僕はクリエイティブという言葉も印象に残ったんですけど、「みる行為はつくる行為」というお話で、岡野さんが「つくる喜び」っておっしゃってましたよね。その“つくる”っていうことに、すごく自分が感じていたことが言語化された気がしました。そこにあるものをそのまま受け入れるのではなくて、見える人からの言葉やいろんな要素から、自分の中のイメージをつくっていくというんですかね。それは僕が多分普段やっていることでもあったんですけど、「その表現があったか!」という感じで、僕はハッとしましたね。
林
なるほど。これ僕もワークショップの活動を続けながら、なにか薄々はそういったことを感じていたんですね。美術を目で見るというのは、情報を受け止めるということだから、受身の行為だと思われがちだけど、岡野さんの言う通り、断片を集めて自分で作り上げる「編集」という行為の方が近いということが、すごくわかりやすく言語化されていて、僕もこのインタビューをしたときになるほどと思いました。大沢さんもまた、その「クリエーション」という部分を、別の言い方で言っているんですよね。
中川
そうですね。大沢さんのスタンプという表現ですよね。いろいろな言葉が出てくることによって、スタンプがポンポンって押されていったり、打ち消しもするという話も、私はすごく面白いなと思いました。複数人で話すからこそ、イメージが打ち消されて、また新しくできてくるクリエイティブな経験だというお話で、2人のお話は使ってる言葉や表現は違えど似てますし、もうめちゃくちゃわかると思いながら読んでいました。
林
大沢さんのこのスタンプの話がすごく面白いと思うんです。「(見える人の言葉を受けて)私の頭の中でポンと押したハンコが、他の誰かの言葉で打ち消されて、最初のハンコを上書きしていくのが、楽しいのかもしれないです」っておっしゃってて。スタンプを押す主体とそれを打ち消す主体は誰なのか?というのが、よく考えると曖昧なんですよね。面白かったのは、ゲームのルールみたいに上書きは他者にしかされないみたいな。自分自身で、意図的に上書きすることはできない。それを聞いて、美術を見るときの主体は、必ずしも“私”だけじゃないのかも知れないということを、僕はそのとき思ったんですよね。上書き自体が楽しいということもかわかる気がして、本当に足場がなくなると困るけど、自分がこうだと思っていたものがちょっと揺らぐことって何かすごく刺激的だし、面白いと思うんですね。大沢さんがそのあと続けて「どんどんスクラップアンドビルドしていくような感覚が楽しい」ともおっしゃっているのですが、そのビルドというのは、さっき岡野さんが言っていたクリエーションにも繋がると思うんです。クリエーションをするには、一旦壊さなきゃいけないということですよね。そこで繋がっているような感じがして、すごく面白かった。
衛藤
その困惑とか、揺らぐところが楽しいというのが、共通している部分だなというのは、僕も感じたんですよね。大沢さんは、そのことを“困惑はわくわく“って表現していましたよね。
中川
大沢さんぐらい、壊すとか打ち消すってはっきり、何かガチャンって言う感じを表現してくれたのが、読んでいてとても気持ちが良くて。それぐらい新鮮な経験として受け止めてもらえということが、スタッフとしても嬉しかったです。
林
でも、本当に困惑する言葉もありますよね。なんていうかな、望まない困惑もありますよね。
衛藤
そうですね。本当に蚊帳の外に出されてしまう困惑。作品の中に入れないとか、そもそも会話の中に入れないっていう状態、健常者中心のルールで会話が進んだときに生じる困惑というのもありますよね。
林
だから、“困惑は楽しい”と単純化した言葉に集約してしまうと、誤解が進んでしまうというもどかしさも半面あったりするので、“複雑さにとどまる”というのは、僕は大事かなと思っています。でも、ちゃんとしたことを言わなきゃっていう先入観が強いときには、困惑も大事な要素だって促すことは、すごく大事ですよね。
鈴村
何か消すとか変更すること、自分が作り上げたイメージがガラガラっと崩れたりとか、急に何か別のものに塗り替えられたりすることに対して、人によっては抵抗がある人ももちろんいるとは思うんですよね。ただ大沢さんと岡野さんの2人に関しては、すごくポジティブで、しかも柔軟に捉えていらっしゃるので、私はそれが面白いなと思いながら読んでいました。
衛藤
やっぱりタイプはわかれるとは思うんですよね。これを楽しめる人も、楽しめないっていう人もいるでしょうね。
鈴村
このワークショップでは困惑してもいいという場作り、空気作りを皆さんがしてくださっているので、それを感じることによって最初は抵抗があった方も、”大丈夫なんだ。ここでは迷っていいんだ”と、なにか安心できる感じは私もしました。数時間のワークショップの中で、だんだん参加者の方の雰囲気が変わっていく様子もわかったりするのですが、何かそのときにもこの方は多分大丈夫だって思われてるなとか、ちょっとこの方は雰囲気が変わったなとか、そういったことが感じられる瞬間がよくあって、多分それはナビゲーターの方々の進行の雰囲気を、掴んでくださってるからなんだろうなという気がしました。
衛藤
今だから思うことなんですけど、大沢さんの記事のなかで、横浜の現代アートを見に行ったときに一対一で案内してくれたそのガイドの方が「こう説明していても、私もよくわからない」って言った時に、自由に楽しめばいいと気づいたという話があったんですけど、それってすごく僕には大事。わからないって言えるってすごい大事だな。だって見える人も困ってるわけじゃないですか。みんなで困ってる、みんなでわからなくなってるっていう状態、そういう場なんだなここはって思ったときに、なんだかすっきりしたというか。それを楽しむ場なんだというのを感じて、僕は一気に面白くなったのを思い出しました。

「『これが私がこの作品を見たという経験なんだ』と自信を持って言える地点が、私の中にはある」
長年この団体に関っている、全盲の視覚障害当事者の中川さん。スタッフ座談会の記事の中で語られた、ご自身の経験の中で言語化されていった「みる」経験のお話は、とても説得力を持って響きました。
鈴村
中川さんが座談会でお話されていたことなのですが、“見た”という経験に関して、ご自分の基準にしていることのお話がとても印象的でした。その部分の引用が、「“自分の言葉で語れるかどうか“というのが一個基準になっています。それが自分の中に落ちたっていうことだから。私は多分(自分の印象に残った作品を)見えてる人が見てるようにはイメージしてないんですけど、自分の言葉で語れるものを、一応これだけ持ってるぞっていうのが最後に残るんですよね」とおっしゃってて、私もなるほどって思ったんですね。その“自分の言葉で語る”っていうのは、どういうことなのかをもうちょっと詳しく伺ってもいいですか。
中川
そうですね。自分の言葉で語れるというのは、自分の中の物語がちゃんと出来ている状態だと思っています。例えば、その作品について語るときに、私は全盲なので、人からもらう言葉しか情報源がないわけなのですが、自分の中にその作品がきちんと落とし込めていなかったり、自分なりに納得していなかったら、私がその作品について語れるのって、他人の言葉のつぎはぎでしかないと思うんですよ。
林
うん。
中川
あの人が言っていたこの言葉と、ちがう人が言ってたあの言葉とをくっつけて、その作品について自分で話してみたところで、多分面白くないし、思い入れもないと思うんですよね。いろいろな人の言葉だとか、その場の空気だったり、そのときの自分の気持ちの変化、そういうものが全部合わさるとき、自分の中で物語が作り上げられていくというか、立ち上がってくるという感覚がある。その時点になって初めて、自分の言葉でその作品について話せる、自分の中の経験として喋ることができる、というところに落ち着くという感じ。
鈴村
他の人の言葉を聞きながら、それとは別の言葉を自分の中でつくり上げるっていう感じですね。
中川
そうですね。別の言葉だったり、あとは自分の中で取り入れたい言葉を選ぶというのも、一つ大事だと思っています。もらった言葉を100%受け止めているわけではないんですよ。その中で引っかかった言葉や表現だったり、鑑賞をしている人たちのリアクションだったり、そういうものを自分で組み合わせるからこそ、「これが私の見た経験なんだ」って、自信みたいなものがうまれる。
見える人に説明された言葉だけをそのまま取り入れると、結局何か正解があるんじゃないかって、やっぱり怖くて自分の経験を話せないということもあると思うんですよ。自分の言葉で話せるっていうところにまで到達したということは、正解云々というよりも、見える人と同じイメージではないかもしれないですけど、「これが私がこの作品を見たという経験なんだ」と自信を持って言える地点が私の中にあるということで、だからこそ私にとって見る経験というものの基準が、自分の言葉で語れることなんですよね。
林
なるほど。
中川
すいません、バーって喋っちゃった(笑)。
林
鈴村さんどうですか。
鈴村
私自身が見たなという気持ちになるときは、もしかしたら自分のものになっていない段階で“見た”と思っているかもしれないなと、ちょっと反省がありましたね。他人から聞いた言葉をつぎはぎするだけではなくって、新たに生み出していくというプロセスが、本当に興味深いなと思いながらお話を伺っていました。

「イメージできてますか?」という質問への違和感
中川さんの「みる」経験のお話からもわかるように、見えない人が見える人と同じように作品をイメージするということが、鑑賞のゴールではない。そこに近づける必要はないにもかかわらず、見える人が見えない人に聞いてしまう質問の話。
林
スタッフの間でもよく出てくる話なのですが、自分にとっての“見る経験が立ち上がる”のを阻むものとして、その場にいる見える人から“イメージできましたか“って聞かれるという問題があるんですね。みる経験が立ち上がろうとするときに、晴眼者からのそういう質問が、それを邪魔するみたいなことはありますか?
中川
そうですね。邪魔するというよりかは、1個ハードルになるかなとは思います。先ほども言いましたが、結局自分の言葉で語れないのは、自分の言葉がその作品そのものを表してないんじゃないかっていう自信のなさがあるからこそ、自分の言葉で話せなくて、他人の言葉を借りて話している。これは結局、誰かが言ってたことのコピペだっていう感覚があるからこそ、自分で踏み込んでいったという感触が残らないんだと思うんですよね。だから、イメージできましたか?私達が見てるのと同じ図を頭に描けましたか?っていうのは、結局自分が立ち上げようとする言葉を、暗に否定されてるような気分になっちゃうというか。
林
うん。
鈴村
今のお話は、座談会の記事にも出てきますよね。林さんもインタビューの中でおっしゃってましたが、私も結構自分がこう聞いてしまうかも知れないですね。
中川
いや聞きたくなる気持ちはすごくわかります。やっぱり共有していないかもしれないというのは、不安じゃないですか。それを解消するために聞いているというのは、気持ちとしてはものすごくわかるんです。でもやっぱり、そこに何か自分が否定されちゃっているのかな?と感じてしまうところがあって。
衛藤
ナビゲーターとしても、見えないナビゲーターでありながら、目の見えない参加者に対して、同じようなことを聞いちゃうときあります。
中川
そう、そう。本当そう。
衛藤
「ついてこれてますか」の意味で聞いてはいるんですけど、でももしかしてプレッシャーを与えちゃっているかなと思う時はありますね。
「対等な立場で自分が思ったことを発言する。それがいいなって思ったんですよね」
最後に岡野さんのインタビュー記事からの引用で、「対等」というキーワードが話題に上りました。
対等であるってどういうことか?再度お話は、立場や属性を単純化してしまうことや、複雑さに目を向けることに立ち戻ります。
林
だからこれって、ガイドですよね。ガイドする・されるという関係が生じているということじゃないですかね。ここにいるみんなが同じイメージができているかどうかというのは、ある程度一つのルールでみんな見ているという思い込みがあるからですよね。「そもそもそういうルールで見てない」って言う人もいるのだけど、そういう人の言葉が出にくくなっているということもあると思います。
鈴村
そうですね。ガイドする・されるという関係が固定化してしまうことに関して、岡野さんがおっしゃっていたこの部分が印象に残っているので、引用しますね。「ソーシャルビューは、対等な立場で自分の思ったことを発言する。見える人も、驚いたり喜んだりして、その言葉をキャッチボールしながらお互い楽しむという感じだから、全然違う。言葉や情報を交換するわけで、関係性が違うから、それがいいなって思ったんですよね」っておっしゃっていて。それがすごく、私も鑑賞のワークショップや美術館でワークショップをする上で、とても重要なことだと思っています。
衛藤
さっきのイメージできますかのところでも、やっぱり僕ら見えない側の中でも、どこかしらで“してもらっている“っていう意識も、“してもらわないと困る“っていう意識もやっぱりあるんですよね。最低限必要な情報というのはあるので、それはガイド的な要素として、必要だなと思う部分もある。逆に見える人は、あるいはその場をつくっていく美術館側としては、どういう意識がありますか?ワークショップをやるときに、やっぱり“してあげないと“っていう意識も当然あるとは思うんですけど。
鈴村
もちろんプログラムを企画することになったら、まず参加する人がどういう人なのかという対象を設定することもありますよね。例えば、小学生とか、中学生以上が参加するとか、何かそういうふうに対象を設定して、その人たちの発達段階とか特性を考慮しながら、対象年齢に合ったプログラムをつくるっていうのが、やっぱり大前提となってくるんですよね。でも一方で、括ってしまうと、例えば小学生という塊で考えると、1人ひとり全然違う人なのに、気をつけてないとその多様性の部分が忘れ去られてしまう。
衛藤
僕らもやっぱり対等でありたいと思うんだけど、どこかでなにか、今対等とは言い難いよなと感じることも、やっぱりあって。それは単純に、してもらってるなって思う、してもらわないとやっぱり前に進まない時もあるし。見える人にとって、対等というのはどういう感じなのかなというのは、たまに迷ったり、考えたりすることはあるんですよね。
鈴村
平等や対等ということに関して、もちろん美術館のスタッフとしてこれをしないといけないとか、した方がいいということはあるかも知れないけれども、でもやっぱり人間対人間じゃないですか。どちらかが優れているとか、劣っているとかいうことはもちろんなく、個性は人それぞれ違う。違いはあるけれど、対等にしなきゃいけないと特別思いながら何かをやったことはないですね。
ただ、特定の人たち向けのプログラムを企画しようとか、準備をしようとなったときに、その人たちをラベリングしてしまうということを無意識にしてしまう時はあって。そういった過程で、なにかいろいろな個別の複雑性がこぼれ落ちてしまうということはあると思うので、気をつけないといけないとは思っています。
林
うん、うん。フラットって多分本当に測れないし、すごく抽象的な概念だと思うので、はっきり目指せないから難しいと思うんだけど、でもなんだか対等じゃないって思う瞬間はあって、それはやっぱり属性と役割が固定されちゃうとき。なにかの”要員”にカウントされていると思った時、それは対等じゃないなって感じます。本来あるべきは、それが対等と呼ぶかわからないですけど、説明する人される人の間に、ウロウロしてる人とかもいていいというか、その立場を選べる状態だから”揺れ動く”っていう表現が僕はしっくりくるんですが、もっと複雑に立場って発生していると思うから、極端に分けてしまうことをちょっと留まりたいとは常々思うことです。
ということで、そろそろお時間ですね。短時間ではなかなか語りきれないのですが、今後こういう時間をちょこちょこつくっていくためにも、話がいのあるようなテーマが盛り込まれたアーカイブサイトを、これからつくっていこうと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。今日はみなさん、どうもありがとうございました。
(編集 森尾さゆり)