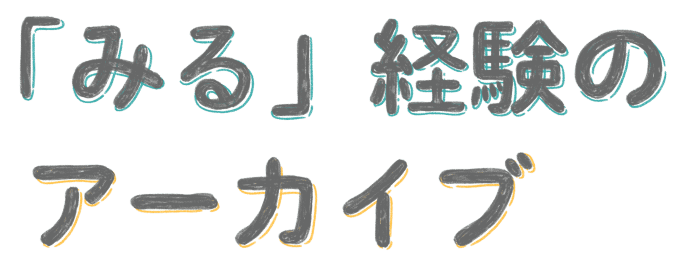「みる」場づくりのインタビュー [前編]亀井幸子さん(元美術館職員)

私たちは普段、目の見える人、見えない人、見えにくい人が言葉を交わしながら美術鑑賞する場をつくっています。
私たちの他にも、全国にはさまざまな立場の人と美術鑑賞をする取組があります。
そしてそこには必ず場づくりを担う人たちがいます。
さまざまな立場の人が安心して「みる」経験をするためには、どんなことを考えどのようにその場をつくってきたのか、その担い手にお話を伺い、「みる」場づくりのインタビューとして紹介します。
徳島県立近代美術館には、障害当事者の方も参加する「アートイベントサポーター」というボランティア組織があります。ここには、障害の有無に関わらず、そこに集まった人々と対話を重ねて一緒に作りあげていく「場」が存在します。組織の立ち上げから関わってこられた亀井幸子さんに、どのようにして場をつくってきたのか、ご自身の経験を交えながら語っていただきました。
プロフィール
亀井幸子さん
徳島県出身。徳島県立近代美術館で、エデュケーターとしてユニバーサル事業やアートイベントサポーターの立ち上げに携わってきた。美術館退職後の現在も、徳島とスリランカに拠点を持ち活動を続けている。
聞き手
林建太
視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップスタッフ。1973年東京生まれ。2012年から活動開始。鑑賞ワークショップの場づくりについては複数のスタッフと対話しながら試行錯誤している。安全な場をつくる方法には正解がないので他の実践者のお話にとても興味がある。
特別支援学校との関わり
林 今日は、徳島県立近代美術館でのユニバーサル事業について、長く現場にいたからこそわかることとか、オフィシャルな話としてではない亀井さん個人のことをお聞きしたいと思っています。最初に、ざっくりと自己紹介というか経緯をお話しいただいてもいいですか。
亀井 はい。私は元々、高校の美術の教員でした。最初の1年が肢体不自由の支援学校、翌年に聴覚支援学校に赴任して、そこで様々な障害のある子どもたちに出会いました。
それまで、美大のお気楽な画学生だったんです。教員になったのも、先輩たちが「教員は絵も描けるし、夏休みもあるし、いいよ!」って言うのを真に受けて(笑)。大学を卒業したすぐの、障害の重い肢体不自由の生徒さんたちとの出会いが、カルチャーショックでした。自分の常識とか価値観とか考えには及ばないことがいっぱいあって。
例えば、授業で、粘土で手をつくる。すると、半身麻痺の生徒がいることに気がついて。「よく手を見てつくろう」って言うと、つくるのは動く方の手なので、当然見つめるのは動かない手だったんですよね。すごく真摯に麻痺した手をつくっているのを見て、「いや…なんて軽はずみに教材を選んじゃったんだろう」って落ち込んで。半身麻痺の生徒さんがいるのは頭ではわかっていたんですけどね。それが、私のスタートです。
でもね、生徒さんたちの方がずっとうわてで、冷静に自分の障害を見つめている姿にまた感動して。自分より色んなことを考えている生徒さんたちが、自分の先生だ…最初からそういう感じでした。
林 はい。
亀井 それからも工業高校や教育委員会などを転々としながら教員をしていました。支援学校では、進行性の病気を持っている重度の生徒さんを担任することが多くて、在学中に亡くなった生徒さんもいて精神的に厳しくて、支援学校じゃなくて高校に戻りたいって希望を出していたんです。一方で、徳島県立近代美術館では、2011年に開館後初めての学芸員の退職を迎えていました。それで、美術館に新規の学芸員ではなく現場の教員が配置された、その第一号が私でした。学校連携に力を入れようということだったんだと思います。
当時、美術館に異動するルートなんてなかったので、夢にも思ってなくて。教員として、美術館の学芸員さんと一緒に教材開発をしたり、出前授業で支援学校へ来てもらったりして子どもたちと美術館をつなげようとし始めたときに、まさか自分がその美術館に異動になるなんて驚きでした。
美術館の仕事は楽しくて!だいたい2、3年で異動なので、私の中では単年度決算。後悔のないように、やれることは目いっぱい入れて、毎年異動したくない!って言って、結局退職までの12年間、美術館にお世話になりました。
林 美術館としてユニバーサル事業が始まったのは2011年頃ですよね。美術館に入られたときに、既にその流れはあったんですか?
亀井 私が美術館に入ってから、障害のことや知っていることを同僚やいろんな人に話していたのが、ユニバーサルミュージアムのきっかけになったんだろうって言われていますね。でも、素地として、学芸員の人たちも、障害のある方が来たら何か対応しようっていう気持ちを持っていましたから、「ユニバーサル事業って亀井さんが来て手話通訳をやったのが一つの転機だったよ」と言われるんですけど、後付けでそう言われているだけではないかと思います。
私の中では特にユニバーサル事業をしている意識は全くなかったです、ただ、教え子に来てほしいなーって。
聴覚支援学校の美術好きだった生徒たちに出逢えるかな、って淡い期待をしていたら、全然来ないんですよね。聴覚障害の人が来てる雰囲気もない。これは自分から動かないと来てくれないと思ったんです。それで単純に手話通訳付きの展示解説を企画して、いろんな方に協力してもらって2011年度末に1回やったんです。あの時は、卒業生1人ぐらい来てくれるかなと思って、必死でしたね。
林 あのとき手話通訳付きのギャラリートークってあんまりなかったですよね、今でこそ、増えていますけれど。
亀井 多分あんまりなかったと思います。
林 ですよね。あと、手話のできる学芸員も相当珍しかったんじゃないですか?
亀井 そうですね。ちょうどその頃手話がだんだん社会的にも認められてきて、ニュースに手話通訳が付き出したりした時期だったかもしれないです。
でもね、結局手話通訳付けたからって、聴覚障害の方が来てくれるわけでもなく。
林 はい、はい。
亀井 実際やってみたら、どこに立てばいいのかも打ち合わせが必要だったし、速さもあれでよかったんだろうか、みたいな振り返りが、解説していただいた学芸員からいっぱい出てきて。1回目ですごく課題が見えた。だから、これは続けられるな、というか続けないといけないなって思いました。
林 やってみて、具体的な課題がいっぱいくっきり見えてきたっていうことなんですね。
亀井 本当にそうです。クリアできた課題もあるし、やればやるほど課題が見えてくる。なので、やめる理由がなかったですね。
盲学校の生徒さんが美術館に来る。全盲の方が1人いるって聞いて、何か作らなきゃって、思いつきでピカソの作品に描かれている人の輪郭線だけを木工用ボンドで盛り上げた触図を作ったんですよ。ほぼA3ぐらいなので両手で持てるし、どうせなら実物大を作れば大きさもわかっていいんじゃないか。私、すごいいいアイディアだと思って実際にやったら、終わった後で「あれは大きすぎて、意味がなかった」って言われて(笑)。
林 ああ(笑)
亀井 なんでですか?って聞いたら、「そんな線だけのものを触っても、覚えていられない」って。子どもたちは、触ることも学んでいる真っ最中で、手のひらより大きなものを触ってもどんな形だったか忘れちゃうよってことで。もっと小さく両手に収まるぐらいの方がいいって言われて、だんだん小型化していったり。
その他にも子どもたちや学校の先生たちに教えてもらいながら、あの手この手でいっぱい試作教材を作りました。
アートイベントサポーターという「チーム」
林 僕が「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」を始めたのも2012年ぐらいなので、ちょうどその辺りなんですよ。で、僕もまさにあの手この手でっていうか。美術館にみんなで出かけていって、いろいろ試しながら、やればやるほど具体的な課題が見えてくるから、ずっと微調整し続けてるみたいなところがあって。
亀井さんとお会いしたのもちょうどその頃なんですよね。僕、すごくよく覚えています。
亀井 そうなんですか! 私は美術館の仕事もよくわからず、とりあえずいろんなところへ出歩いてるときでもありました。
林 エイブルアートさん(※1)がやっていた“みんなの美術館プロジェクト”の報告会の中の同じテーブルに亀井さんと僕が座ってたんですよね。僕もまさに実践の場を見て歩いていたときだったので、「ああ、美術館の中の人もこういうところに来て、ちゃんとやろうとしてるんだ」って、頼もしいというか、先が明るい感じがしたのをすごく覚えています。あのときはどうでした?
亀井 林さんが目の見えない人と一緒に作品を見て話をするんだっていうのを聞いて、どういうことなんだろう?ってすごく興味を持って。なので、あれから追っかけをして、何度も林さんのワークショップに申し込みました。
林 そうですね。何度も参加してくださって。
 ワークショップに参加中の亀井さんの写真
ワークショップに参加中の亀井さんの写真
亀井 抽選で断られたこともあるし、見学させていただいたこともありました。
それで自分が参加したときには、実際に目の見えない人とも一緒に鑑賞する面白さを実感できて、自分の職場で何かやるときのベースというか、支えになりました。少々失敗しても、次は、こうしようって気持ちを持ち続けられたのは、ここで「絶対面白いぞこれは!」っていう実感が持てていたからですね。
せっかく遠くから来ているんだし、スタッフのミーティングにも入りますか?って言ってくれて、何度か同席させてもらったこともあって。こんなにシビアに打ち合わせをして、こんなふうに反省をして次に生かしていくんだな、自分には真似できそうにないけど、でもこういうふうにやっていくんだなって感じたのも、私の中では支えでしたね。
林 シビアって、どんな感じですか? 厳しい感じでしたか?
亀井 ある発言に対してその意図や背景を共有して理解し合おうっていう姿勢っていうんですかね。ファシリテーターの「こういうときにこうすればよかったんじゃないか」といった反省の言葉を聞くのが新鮮でした。美術館では単独で計画して1人で突っ走ってしまうしかない面もあって。話がまとまらなくて大変そうだなっていうのもあるんですけど、いろんな立場の人とチームでつくり上げていく感じって羨ましかったですね。
林 あー、なるほど。
亀井 お話してて気がついたんですけど、今のユニバーサル事業のアートイベントサポーターの方たちとの関係性っていうのは、そういうのを自分が望んでたんだなと。
アートイベントサポーターを作ったときに、ボランティアを頼む人と引き受ける人とか、障害者をサポートする人と支援を受ける人とか、そういう関係にとらわれないチームにしたかったんですね。そのイメージのベースは、今思うと、林さんたちのあの真剣な話し合い、見える見えないとかに関係なく本当にみんながいろんな意見を出し合っていくっていう関係が、絶対どこか意識の中にあったんだろうなって思います。
林 そっか…。僕も、サポーターの方たちと美術館の関係が、すごく独特で、すごくいい関係だよなって思ってたんですよ。
2月に僕らが行ったとき(※2)に使わせてもらったお部屋でいつも会議とかされてるんですか? 積み重ねてきた熱気が残っているかのようでした。僕らがお弁当を食べていたら、準備する時間にさしかかったみたいで、サポーターの皆さんがわらわらと集まってきたんです。あの時の皆さんの“自分たちの仕事場だ”みたいな感じが、なんかすごく…“いいものを作っている工房に来た”みたいな感じがあって。そこに積み重なってきた時間を、ちらっと垣間見た瞬間でした。
亀井 そんなふうに言ってくださると嬉しいですね。
林 アートイベントサポーターの特徴って、障害当事者の人も、いろんな属性の人たちがいますよね。その人たちをお客さん扱いじゃなくてスタッフとして招き入れていて、喧々諤々、アイディアや意見を出せる雰囲気があるっていうのは、あれはどうやって…?
亀井 やっぱりね、最初からじゃなくて。最初は「いやあ、私達目の見えないもののためにありがとうございます」みたいなスタンスで参加してくださっていたと思うんですけど、だんだん、鑑賞の面白さとかが深まっていくと、意見や思いが、ポロッポロッとこぼれ出るようになって。
アートイベントサポーターのお一人で全盲の方が、触図を「私、本当はこれ触りたくない」っておっしゃったんです。「一生懸命作ってくれてるから触ってたけど、本当はこういうんじゃなくてもっと自由に頭の中でイメージにしたい。触ると、一つの絵の解釈を理解しないといけない、一つの正解を見るような気がして、私は嫌だ」って言われたときには、もう目からウロコでした。
対話鑑賞の面白さって、同じものを見ても意見がわかれるところで。決してデタラメじゃなくて、ちゃんと根拠が絵の中にあったり、その方のイメージとか記憶がつながってたりする。言葉だとそんなふうにいろんな意見が出てくるのに、触図とか情報保障って一通りしかない。それは確かに窮屈で、これを理解してくださいねって言ってるようなものだったな、と、反省をしました。
林 それは、嫌だって言える環境があるってことですよね。
亀井 もうね、そこまでに何年かかかったんですよ。
それまでは、せっかく一生懸命私達のために作ってくれたからって、黙って触ってくれてたんです。
林 そっか。最初はお客さんとして気を使って言わなかったんですね。
亀井 はい、もう私達のためにこんなことしてくれてありがとう、みたいなスタンスで。
林 でも、言えるようになった。それには何があったんですか?時間をかけてその場を作っていったんですか?
亀井 やっぱり時間。あと、一緒にユニバーサル事業をやっていた学芸員の存在ですね。
ボランティアしたいっていう方は、やりがいとか生きがいとかを美術館に求めてきてくださってると思うので、あなたたち美術館の都合のいいように働いてね、じゃなくて、自分たちのワークショップなんだ、自分たちが作ってるんだ、っていう感覚が持てることが大事だと思うんです。最初は「これの触図作ります。展覧会のメインの代表作なんで。」みたいなことで作業を下ろしてたんですけど、いやいや違うぞと。とりあえずこれ作ってでは絶対楽しくないし、良い触図はできないだろうって、はたと気が付いて反省をしてですね。
ユニバーサル事業の展覧会では、出品予定の作品を事前に20枚ぐらい教えてもらって、その中でどの作品で一緒に話したいか、担当学芸員と一緒に時間をかけて話をするようになったんです。今思うとこれが本当に重要だったなと思います。
以前、ウサギが描かれた作品が出品予定だったことがありました。横向きのウサギと手前に葉っぱがちょっとあるだけの非常に情報の少ない水墨画なんですけど、目力がすごいんです。ウサギの向いている視線の先は絵がないので、何を見ているかは全くわからない。サポーターの方たちとの対話鑑賞のときに、「ウサギは何を見ているんだろう?」という話に辿り着いた時に、見える見えない関係なく、すごく盛り上がって。ああ、何を見たいかは、こんなふうにして決めていけばいいんだって。それ以降、どの作品の触図をつくるかは、サポーターの皆さんと一緒に話し合うようになりました。
また、ユニバーサル美術館展では、最終的には担当学芸員が作品を決めるんですが、決まる前に「展覧会でこの作品が見たい!」といったサポーターのいろいろな思いが言えるようなミーティングの場が生まれました。それはすごいことだと思ってました。
林 つまり、スタッフの準備の段階、バックヤードでの話ですよね。
亀井 そうです、そうです。
林 ですよね。それがすごいなと思うんですよ、バックヤードにも、美術館の職員とそうでない人、障害のある人とない人が活発に対話をする場ができているっていうのが。
亀井 どういう作品を見て、どの作品で触図を作るかっていう話し合いをサポーター中心で学芸員も交えて、一緒に決めていくようになってから、サポーターの意識も変わっていったんじゃないかなと思います。
2014年か15年ぐらいにサポーターの組織ができたんですけど、その前からもお手伝いしてもらったりしてたので10年近く。その中で、美術館の職員もちょっとずつ成長というか変化もしてこられたし、サポーター自身も自分の意見が役立つことを実感してもらう中で、本音をちょっとずつ言ってくれるようになったのかなと。
そのあたりで、当初は軽い気持ちで参加してくださっていたサポーターの方も、すごくいろんな意見を言ってくださるようになって、私の想定外の素敵な変化でした。まだまだ遠慮してるところもあると思うんですけど、これからも続いていけば、またもっと違う関係が深まっていくのかな、と、楽しみにしています。
林 みなさんの中には、プログラムっていう一部じゃなくて、もう美術館そのものを作ってるっていう意識があるんですかね。
亀井 精神疾患がある方、社会での生きづらさを感じてる方とかが、ふとワークショップに参加してくださったりすると、イベントサポーターがね、すごく勧誘するんですよ。
林 へえ(笑)
亀井 「そんな障害あっても関係ない。面白いからいっぺん覗きにおいで」って誘ってるんですよ。それで心地いいと思ってくださった方は、残ってくださって。生きづらさ含めていろんな障害のある方、みなさんそれぞれに会社とか家庭では、自分が駄目なところばかりを気にしているのに、ここに来ると、得意なこととか喜んでもらえること、できることがあるっていうのを、実感してくださるみたいです。
イベントサポーターのはじまりは、保育所を退職した先生たちが、子どもたちのアート活動を支えるボランティアをしたいと言ってくださったのがきっかけだったんです。
子どもは、作品に触れそうになったり叱られたりする場面があるんですよね。だから、そうなる前にグループから離れた子と手を繋いだり話し相手になったりすれば、先生が安心して子ども達を美術館に連れて来られるんじゃないかと。
その先生たちがユニバーサル事業にも協力してくださるようになって。この方々が子どもたちだけでなくどの人に対しても、おおらかで優しいんです。どんな人でもどうぞいらっしゃい!って。ふらっとワークショップに参加してくださった方が「私、実は…」ってぽろっと自分のことを語りはじめたところを見たことがあります。
そういう、本当に恵まれた人たちに囲まれてやってきたので、私自身は何もしてない。何かこんなことやりたいとか、好きなこと言ってただけ。ほんとにそんな感じで。
林 いや、でも、やっぱり何かはしてると思うんですよね。亀井さんがつくってる場というか…。
注1)NPO法人エイブル・アート・ジャパン。ホームページへのリンク
「みんなの美術館プロジェクト」は2008年~2012年の4年間に実施されたプロジェクト。
注2)2024年2月23日・24日に徳島県立近代美術館で開催した「鑑賞ワークショップ&レシピ持ち寄り座談会」の時のこと
(編集:熊谷香菜子)