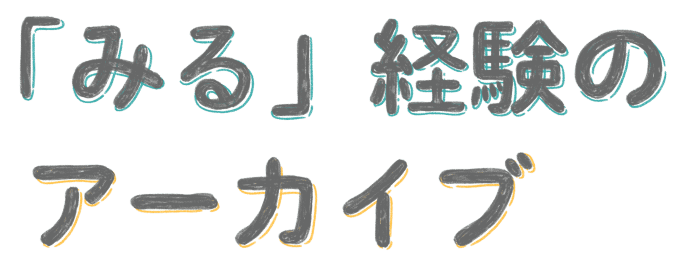「みる」経験のインタビュー 鈴木恵子さん
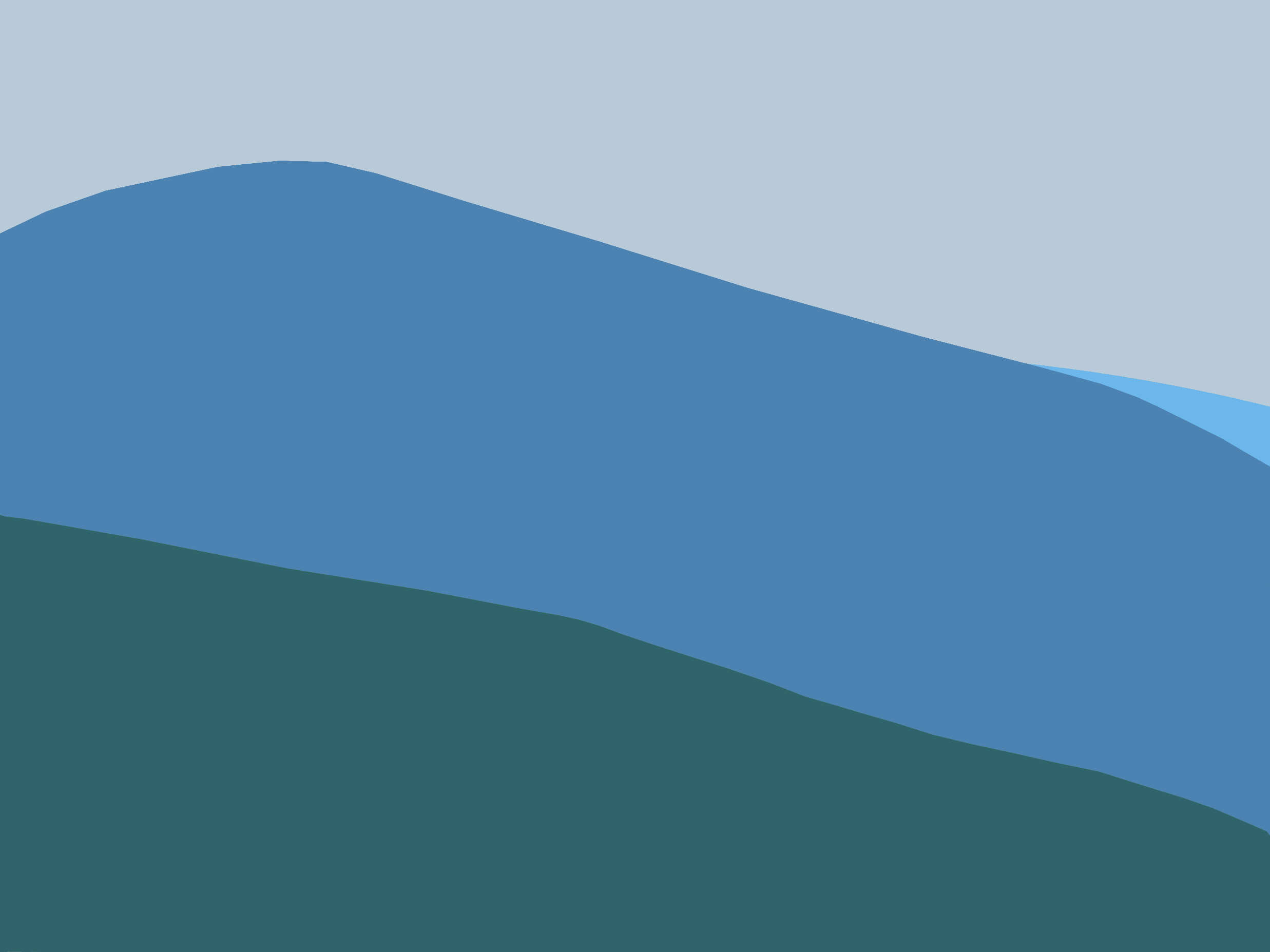
このインタビューは、目の見える人、見えない人、見えにくい人、さまざまな立場の人に「みる」経験をインタビューするシリーズです。
美術を鑑賞する方法には、目で見るだけではなく、目の見える人と見えない人が一緒に言葉を交わしながら「みる」方法や、立体作品に手で触れながら「みる」方法もあります。それぞれの経験は、記憶や経験、他者の言葉など、環境との相互作用によって変化していきます。その変化のプロセスに目を向けて、さまざまな「みる」経験をインタビューとして記録します。
言葉を聞いて、描く側に立つ。鈴木さんは、鑑賞するために、まずは目の前にある絵を、できるだけ自分の頭の中のキャンバスに再現していきます。そして、絵が完成すると、疑問がどんどん沸いてくるのだそう。そんな鈴木さんから出てくる疑問に不思議な魅力を感じた聞き手とともに、ある日の鑑賞会での、鈴木さんの「みる」プロセスをじっくりと紐解いていきます。
プロフィール
鈴木恵子さん
神奈川県在住。マッサージ師として会社勤務。網膜色素変性症により、現在は全盲。
見えない白鳥さんとアートを見に行く。を読んでから、見えなくても美術鑑賞が出来るのかと衝撃を受け、自分もやってみたいと思い立ち、いろいろなワークショップに参加。そこで知り合った晴眼者の方と、いまでは、個人的にも美術館に足を運んでいる。盲導犬使用者でもあり、今は3頭目のパートナーと歩いている。
聞き手
林建太 (視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップスタッフ)
視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップスタッフ。1973年東京生まれ。鑑賞ワークショップでは主にナビゲータを務めている。美術や映画が好きで、そのことを語る会話の不思議さにも興味がある。
いろいろな見方といろいろな楽しさ
林 昨日も美術館に行かれてたんですか?
鈴木 そうなんです。東京都美術館の「障害のある方のための特別鑑賞会」に行ってきました。お友達に教えてもらって、申し込んだら無事当選しまして。
林 東京都美術館の特別鑑賞会には初めて行かれたんですか?
鈴木 はい。今回初めて行ってきました。
林 美術館に行く時には、展覧会で選ぶというより、そういう催しがある時に行く感じですか?
鈴木 そうですね。私はガイドさんとしゃべりながら歩くので、一般の方がいると気を遣うんですよね。そういう会では、皆さん普通にしゃべって、杖の音もコツコツしているし、そういう音を全然気にしていないから私も気が楽なので、できればそういう日を選んで行っています。質問もできるし。
林 じゃあ、昨日は楽しめましたか?
鈴木 はい、楽しかったです。
林 今回は、ミロの展覧会でしたよね。
鈴木 ミロって抽象画なんですね?今回、説明する方もすごく苦労されていて。触図を触らせてもらって、あぁなるほどね、っていう感じでしたね。
林 そういう時は、触りながらお話もされるんですか?
鈴木 美術館の方が「触りませんか?」って声をかけてくださって、その方としゃべりながら見ました。「ミロは控えめで、大きい絵でもサインをちっちゃく書くのが特徴ですね」とか、そういうことも教えていただけました。
林 以前、モネを見に行かれたというのも上野でしたっけ?
鈴木 はい、上野の西洋美術館に。これは美術に詳しいお友達と、普通の一般公開日に行って、やっぱりすごく混んでましたね。なので、結構ごった返している中で説明を聞いて。
私、中途の全盲で、15,16年ぐらい前までは弱視、学生時代も弱視だったので、モネの絵はぼんやり見た記憶があったんです。だから、その時の印象があったんですけど、やっぱり色覚とか明暗とかにちょっと違いがあって。私の印象では、睡蓮は青っぽくて暗いイメージだったんですけど、説明してもらうと「いや、パステル調のもある」とか「橋が全部に描いてあって」って言われて、「え、橋なんてありました?」みたいな発見があったり。私が見た記憶と実際とのギャップを痛感しながら、逆に楽しめましたね。
林 そういう時は、絵そのものを思い浮かべているんですか?
鈴木 はい、モネの時はそうでした。昔はそんなに美術に興味がなかったので、教科書に載ってるレベルくらいのものですけど、見た記憶がある作品の時は、それと重ね合わせていきます。そうすると「えっ、そうなんだ」っていう驚きがあったり、印象が変化していくんですよね。「私が見たのはやっぱり違ってたんだな」と感じることもありますけど、逆にそういうのを聞いて、どんどん頭の中で修正されて、「ああ、こういう絵も描く人なんだ」とか「こんな絵だったんだ」みたいな新しい発見があるのが楽しいですね。
林 じゃあ、モネの絵に橋があるって言われたら、思い浮かべた絵に橋が描き加わる感じなんですか?
鈴木 そうですね。橋があって、垂れ下がっている緑の葉っぱがあって、って聞いて、「ええ、そんなのもあるんだ!」って驚きながら付け加えていって。モネの睡蓮ってたくさん作品があることも知らなかったので、私が昔見たモネの睡蓮ってどれなんだろう?と思ったり。「でも、橋はみんなありますよ」って言われたので、「ああ、やっぱり橋ってあるんだ」とかね。そんな感じで鑑賞してます。
林 なるほど。
鈴木 私の頭の中の出来上がりと目の前の絵は、一致はしてないと思うんですけど、私なりに想像するっていうのも、すごく楽しいですね。しゃべる方も、「1枚の絵を、1人だったらさっと見て、ふーんって感じで通り過ぎるんだけど、こうやって人に説明しなきゃいけないと思うと、じっくり細かく見るから、私も楽しい」って言ってくださるので、それを聞くのも私も嬉しいし、そこまで見て喋ってくれると、なんだか、一緒に見ている気分になれますね。
林 触図も言葉も、とても臨機応変に活用している感じなんですね。言葉を使って見るのは、鈴木さんにとっては有効な方法ですか?
鈴木 そうですね。そこにいる方に言葉で説明してもらわないと、何が描かれているかも分からないので。人によっても説明の仕方が違うので、「あ、この人はこういうふうに表現する人なんだ」っていうところを感じるのも、楽しいです。
林 そうなんですね。鈴木さんは、割とどんな球が来てもというか、どんな言葉が来てもキャッチできる感じですか?
鈴木 うーん、どんな球が来てもというか、「この人はこういう感覚を持って、この絵を見てるんだなぁ」みたいな感じですね。モネやミロは、ガイドさんと2人で行って説明していただいたんですけど、林さん達がやっている鑑賞ワークショップの形式だと、いろんな人の意見が飛び交うから、同じ絵を見ても好き嫌いって出るんだなとか、印象が違うんだなって、そういうのを受けとることができるのが、私は楽しいです。
林 言葉をキャッチするだけじゃなく、言葉が飛び交う様子も楽しんでいる感じなんですね。
言葉を聞いて描く側に立つ
林 この間の横浜美術館の鑑賞会では、《緑蔭》※1っていう作品を見ましたよね。
鈴木 ええ、4人の女の人の絵。

《緑蔭》を鑑賞しているワークショップ中の写真(写真提供:横浜美術館)
林 はい。あれは絵の印象が分かれましたよね。そんな時は頭の中の絵はどうなるんですか?
鈴木 私の場合は、描く側に立つって言うとおこがましいんですけど、頭の中で描いていくんですよ。 ブドウ棚がある、女の人達は2人が日本の着物で、2人は韓国の着物、背景は穏やかです、なんて言葉を聞いて、どんどん頭の中でそれを配置して、絵のイメージを膨らませていくんです。
「でも目はきつい、みんな怖い顔をしてます」って言うから、なんでだろう?と私は思ったんですけど、「怖い顔をしているから、ちょっと」って言う人と、「私は好き」って言う人がいるのかな?って思ったりしました。
林 つまり、頭の中の絵自体はそんなに変わらなくて、その絵を鈴木さんも一緒に見ながら鑑賞している感じですか。
鈴木 はい。
林 私、あの時の鈴木さんの質問がすごく印象に残っているんです。例えば、「韓国の着物の人と日本の着物の人がいて、髪型は違うんですか?」っていう質問。鋭いというか、言われてみればポイントになっているところだなと。それは、なぜ気になったんですか?
鈴木 「日本の着物の人はたぶん日本人で、韓国の着物の人は韓国の方なのかしらね」って言う方がいたから、「じゃあ日本人は日本髪かな?外国の人は違う髪型かな?」って単純に思っただけで。
林 そうか、それはたしかに自然な流れですよね。
鈴木 だから、「全員おかっぱです」って言われて、「あっ、そうなんだ」と思って。
林 それまでの時点では、日本髪っぽいものが仮のイメージとして鈴木さんの絵には置かれているんですか?
鈴木 そうですね。それで、韓国の人だったら、長い髪を後ろで1つに結んでいるイメージがなんとなくあったので。
林 ああ、わかってきました。私は、鈴木さんの質問を聞いていて、鈴木さんの中にすでにある絵を見ながらお話をしてる感じがしたんです。わからないから教えてっていう質問の仕方じゃなくて、「ここってこうかな?」って、具体的な手触りのある確認の仕方に感じたんです。
鈴木 ああ、そうですね。
林 「着物の柄は明るい感じですか?」と聞いていたのは、そこが空白だから埋めようということですか?
鈴木 そうです。
林 描き手の視点に立つのは、いつもですか? 例えば、モネの時もそうでしたか?
鈴木 モネの時もそうですね。作者の立場に立って、皆さんの言葉に沿って目の前の絵を頭の中で描いていくんですよね。
林 その時、本物の作者は出てこないんですか?
鈴木 本物の作者はあんまり気にしたことはないです。
林 じゃあ、キャンバスの前に立ってるのは、鈴木さんなんですね。
鈴木 はい。それで最後に出来上がったときに、初めて作者の立場に立って、最後の疑問。「私なら笑顔にするけど、なんで作者は鋭い目にしたのかな?」と。教師が描いたってことだから、教え子を描くなら笑顔にしてあげればいいのになぁと。
林 作者自身は出てこないけど、そこまでいくと作者と話ができるようになる。
鈴木 そうですね、出来上がった時点で作者の気持ちを考えるって感じかなぁ。
林 ああ、そうだ、確かにそんな流れでした。あの時、鈴木さんの質問がやけに具体的だと思ったんですよね。「あれ?前に見たことあるのかな?」っていうぐらい。
鈴木 いえいえ、初めてでした。
林 初めて見たけど、すでに鈴木さんの頭の中で絵を描いているから、私はそういう印象を抱いたのかもしれないですね。
言葉を視覚的な経験に変えて鑑賞する
鈴木 その次に見た《ヨコハマ・ナイト》※2も、やっぱり頭の中で描いていました。手前が夜の街で、酒場で飲んでる人もいて、2階からちょっと顔を出している人もいて、っていうのを全部頭の中で想像して。
林 あの絵はすごく要素が多かったので、いろんな言葉が積み重なっていきましたよね。その時の「いっぱい人がいるっていうのはわかったけど、みんな男性なんですか?」っていう質問も興味深かったです。言われてみれば、確かに気になるし。それは言葉として、男性がいっぱい出てきたからですか?その時、鈴木さんの絵の方はどうなっていたんですか?
鈴木 夜のいわゆる飲み屋街みたいなイメージを私は描いてたんですよ。時代が、大正・明治みたいだったので、「その時代に女の人もこういう夜の街に出られたのかな?女の人って描かれているのかな?」と思ったんです。
林 あ、じゃあ、それは自分で描いた絵を見てというより、時代背景として?
鈴木 それは、描いてる途中ですね。言われた通りに人を配置していくと、みんな男性っぽかったから、それでいいのかなっていう確認のつもりで。
林 そう、私も、その質問で確認しているように感じたんですよね。
鈴木 それで、「賑やかな街の向こうに畑と山と海も見えます」って言われて、すごく対照的なものもあるんだなぁと思って。「ヨコハマ・ナイト」だったら、私なら、にぎやかな街中だけしか描かないのに、「なんで海や畑まで描いたのかな?」っていう疑問が、絵が完成した時に出てきたんですよ。
林 ああ。
鈴木 「作者が、わざわざ海や畑も描いたのは何の意味があるんだろう?」って。
林 鈴木さんと鑑賞していて何が面白かったのかが、わかってきました。いろんなことを積み重ねていって割と終盤の方で、鈴木さんは「問い」にたどり着くんですよ。そういった「問い」を出してくださるのが、すごく、お話ししていて面白かったんですよね。
鈴木 そうですか。私は単純に楽しく見させてもらっていて、疑問が思い浮かぶんです。
林 それが鈴木さんの見方なんですかね。
鈴木 そうですね。説明してくださったものを絵に付け足していって、そのうちに、これでいいのかな?と思って聞いて。
林 細かい材料は聞きながら足していく感じですよね。そうやって鈴木さんが描き込んでいって、一応絵としては完成するじゃないですか。でも、そこで終わりじゃなくて、むしろそこから始まる感じがするんですよ。
鈴木 ああ、私の疑問ですよね。私ならこうするのにっていう思いが出てきます。まあ、こういう絵を描きたかったんだなぁって、それで満足しちゃって出ない時もあるんですけど。
林 疑問が出ない場合もあるんですね。
鈴木 ありますね。
林 それは別にどっちがいいというわけでもないんですか。
鈴木 ええ、どっちがいいというわけではないです。あの時、「なんで作者は海や畑まで描いたのかな?」って聞いたら、どなたかが「街全体を描いたんじゃないですか?」って言ってましたよね?
林 そうですね、「海も含めて横浜だからじゃないか」って。
鈴木 そうすると、次に「じゃあ、これは実際に見えるところから描いたのかな?」っていう疑問が出てきて。
林 その絵を想像で作者が描いたのか、それとも実際の場所で見ながら描いたのか。どうしてその疑問が出たんですか?
鈴木 実際にこの景色を見ないと、海や畑や山まで足そうとは思わないんじゃないか、だから作者はどこかで一度はこの景色を見てるんじゃないか、と思ったんです。
林 私は、もし絵が見えていたらその疑問って出るのかなぁと思ったんですよ。絵の前に立った瞬間に、構図がパッと一目瞭然で目に入ってきて、私にはその疑問が湧かなかったんです。確かにあの絵は、街も遠くの山も1つの絵の中に収まって、遠くまで眺めている構図がすごく特徴的なんです。
鈴木 今の時代だったら、ドローンを飛ばして写真を撮るのも簡単だけど、上から見た絵を想像して描くのって大変じゃないかと思って。
林 それは、鈴木さんが自分で描いてるからそう思ったんですかね?
鈴木 うーん、そうかも…? 最初に、上から商店街を見た絵だって言われたからかもしれないです。それで私は、見える場所ってあるのかな? と単純に思っただけ。
林 いや、本当に単純な質問なんですけど、それが、なんだか不思議なんですよね。私は、その質問と、鈴木さんが自分で頭の中に描いているっていうことが関係している気がするんです。作者は描こうとして描いているわけじゃないですか。ここには真っ暗な海を入れたいと思って描いている。鈴木さんは、自分で描きながら、作者の手の動きをなぞっているんですかね?
鈴木 そうなのかなぁ…。最初は、もちろん見えないから頭の中は真っ白なんですけど、夜の街中の風景です、酒屋さんがある、人がいるって言葉を聞いて、どんどん描いて付け足して。後から、この先には畑と海が見えますとか言われて…
林 そこで、ちっちゃな疑問が初めて湧くんですか?街中の絵のはずなのになんで海が出てくるんだ?と。
鈴木 そこでは「ああ、そうなんだ」と思っています。完成に近づいて、こんな感じの絵なんだろうなぁっていうところで、初めて疑問が出ます。
林 そうか。鈴木さんは、言葉を言葉のまま意味として理解しているのではなくて、言葉を使って頭の中で絵を描いているんですよね。だからそれはきっと、鈴木さんにとって「絵を眺める」っていう、視覚的な経験になっているんじゃないでしょうか。
言われたことを言葉のままで理解していたら、さっきの疑問は出ないと思うんですよね。鈴木さんの頭の中に、すごく遠くまで見えてるっていう構図の絵が描きあがっていて、それを眺めているから、作者はこれを見たのか?見ていないのか?っていう疑問が出てくるんじゃないでしょうか?
鈴木 そうかもしれないですね。 自分で描いてるつもりになっているので。
林 その時、鈴木さんにも見えちゃってるわけですよね。海とか山とか、省いたっていいのに、ここに見えちゃってるから。
鈴木 はい。私ならそんな遠くの海や山まで想像がつかないから、作者はその景色を見たんじゃないか?って。
林 ああ、ちょっとわかった気がします。鈴木さんが、絵を眺めながら質問を出している感じがしていたんですよ。そういう自覚はあんまりないですか?
鈴木 うーん、自覚はないというか、言葉のままじゃあ全然絵が浮かばないので、絵を想像するためには自分で描かないと。
林 そうか。もしかしたら、見えている人は絵を見るときに、時間をかけて丁寧に描く作業をしていないかもしれないと思いました。一瞬で全部が入ってくるので、特に、遠くの暗い海とか山とかの、入れなくてもいいんじゃないかと思うような情報ほど省略してしまって。でも、鈴木さんは、それを意識的に描いているわけですよね。なんで海があるんだろうって思いながらも、省略せずに。
鈴木 ええ、言われたので足しています。
林 見えている人は省略しちゃってるんじゃないですかね。鈴木さんの「なんで海を描いたんだろう?」っていう疑問は、この絵の中で、海は特に見るべき部分じゃないと思って省略しちゃっている人からは、絶対出ないと思うんですよ。
鈴木 でも、そう聞いたら、「海もセットで横浜なんですよ」っておっしゃった方がいましたよね?
林 たぶん、鈴木さんに聞かれなかったら、その解釈も出てこなかったと思うんです。あの《ヨコハマ・ナイト》っていうタイトルが、そこまでたくさんのものを含んでいるとは思わずに通り過ぎちゃっていたかもしれない。

《ヨコハマ・ナイト》を鑑賞しているワークショップ中の写真 (写真提供:横浜美術館)
林 鈴木さんの「みる」プロセスで必要な工程は、まず、描くことですかね?
鈴木 そうです。それで、だいたいできてくると、初めて作者が登場して、作者の思いと自分の思いの違いとか、疑問がどんどん出てくる。
林 それで、その疑問を場に投げかけるじゃないですか。すると、みんなが「ほぉー」みたいな空気になってたんですよ。
鈴木 あ、そうですか、全然気にしてなかった(笑)
林 鈴木さんは、そこからも楽しいんでしょう?
鈴木 楽しいです。いろんな人がいろんなことを言ってくれるので。同じ絵を見ても、これだけみんな違う感想を言うっていうことも楽しいですね。
林 終盤になったら、もう絵自体はそんな描き換わることはないんですか。
鈴木 ないです。 出来上がった時点からは、作者の考え方を感じるだけです。
林 そうなんですね。いやー、面白いです。
鈴木 そんなに面白いですかね、私にとっては普通の見方なので(笑)
絵画ってそうやって楽しむものじゃないですか? 実際のものが見えないので、自分の頭の中で同じような絵を作っていくしかないなぁと思ってるんですよね、美術鑑賞って。
林 私も、鑑賞ってただ情報を受け取るだけの行為ではなくって、作ることとか描くこととすごく結びついた、クリエイティブなことだと思うんです。それで、鈴木さんのお話を聞いて面白いと思うのは、作者が描いたものをすごく律儀に、鈴木さんは「え、ここに海いる?」って思いながらも、手はちゃんと海を描いてるっていうところで。
鈴木 実際の絵に海があるから、とりあえず描いておきますね。だって作者は描いたんだから。
林 そこは、ねじ曲げないんですね。
鈴木 皆さんが見てる絵を私も見たいっていうか、同じものを見て感想を言いたいと思うと、私には必要ないと思っても、作者が描いてるし実際にあるんだから、できるだけ同じように作ってるつもりではいるんです。
林 それが鈴木さんの鑑賞にとって大事な工程なんですね。
鈴木 そして、出来上がった段階で疑問が出てくる。
林 作品を見るってそうですよね。作者と自分のずれが発見されるというか、そうすることで作者に出会うというか。
鈴木 そう。だからこういう大勢で見るワークショップは、私はすっごい楽しいです。
林 確かに相性がいいかもしれないですね。
注1)2025年横浜美術館「おかえり、ヨコハマ」展でのワークショップで鑑賞した片岡球子《緑蔭》
横浜美術館コレクション検索の作品紹介ページ
https://inventory.yokohama.art.museum/10444
注2)2025年横浜美術館「おかえり、ヨコハマ」展でのワークショップで鑑賞した清水登之《ヨコハマ・ナイト》
横浜美術館コレクション検索の作品紹介ページ
https://inventory.yokohama.art.museum/50
(編集 熊谷香菜子)