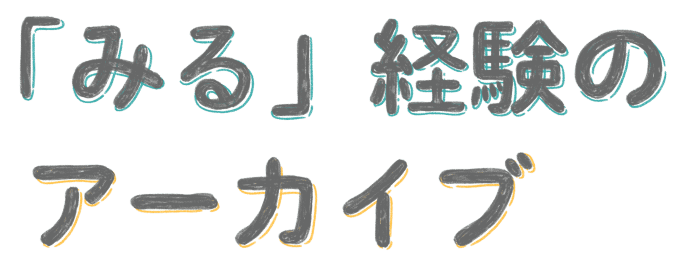「みる」経験のインタビュー 佐藤・コルヴィーさん

このインタビューは、目の見える人、見えない人、見えにくい人、さまざまな立場の人に「みる」経験をインタビューするシリーズです。
美術を鑑賞する方法には、目で見るだけではなく、目の見える人と見えない人が一緒に言葉を交わしながら「みる」方法や、触れながら「みる」方法もあります。
それぞれの経験は、記憶や経験、他者の言葉など、環境との相互作用によって変化していきます。その変化のプロセスに目を向けて、さまざまな「みる」経験をインタビューとして記録します。
写真は絵画に比べて、出てくる言葉の安定度が高い。しかし、客観性が全てではなさそうで…。日常的に芸術作品に触れてきた、そしてこれからもそうであろう佐藤さんのインタビューは、写真を見ながら対話鑑賞をする面白さはどこから生まれるのかを探る対話になりました。終盤で語られた、わからないことの大切さは、見える見えないに関係なくすべての鑑賞者に通じています。
プロフィール
佐藤・コルヴィーさん 東京都在住
私は早い時期に黄斑変性症(錐体細胞ジストロフィー)と診断され、見ようとする中心部が見えていない弱視でした。当時これは、はた目には意識される事はほぼなく、日常においても家族を含め、特別扱いはほとんどありませんでした。しかし日々現実を生きる私の内情は厳しく、いつも異常に緊張していたと思います。こういう私に今日にいたるまで一貫しているのは「私は人間は嫌いだが、人間が生きている事、人間が作ってきたものには興味がある」という事です。これからもこのコンセプトを維持しながら演劇や映画・落語や芸能そして美術の世界にも心の自由と遊びを求めて放浪し続けたいと思います。余談ですが10代のころに、もし、おばばになるまで生きたとしても最後まで青臭くありたいと考えました。その通りになっているようです。
聞き手
林建太
視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップスタッフ。1973年東京生まれ。鑑賞ワークショップでは主にナビゲータを務めている。美術や映画が好きで、そのことを語る会話の不思議さにも興味がある。
美術館の空気
林 美術館にはすごくたくさん行ってらっしゃるんですよね。私達のワークショップにも色々と参加してくださっていますが、昔から美術館に行かれていたんですか?
佐藤 はい。子どもの頃から、よく父と美術館とか博物館に行っていたので、弱視になってからも美術館に行くのは自然なことでした。
林 見えなくなったのはいつ頃なんですか?
佐藤 ずっと弱視だったのが、この30年かけてだんだん進行してきましたね。今は明るさや、細かくちらっと見える部分はあるけど、まとまった画像にはならなくて、もう弱視とは言えないですね。以前はまだ周りに視野があったから、興味ある展覧会には行ってたけど、見えにくくなってくると特に1人で行くのは敷居が高くなりましたね。そうすると連れがあるときとか90年代に入って展覧会に音声ガイドが付くようになって、そういうところに行ってましたね。その後ですね、ここの鑑賞ワークショップと出会ったのは。
林 我々よりも前からやっていたNPOとかもありましたけど、そういうものは?
佐藤 いや、知らなかったですね。
林 行く機会は多少限られてきてはいるけど、その中でも行ける展覧会を選んで行くっていう感じですか?
佐藤 そうですね、はい。
林 どういう展覧会に行くか、選ぶポイントってあるんですか?
佐藤 1つは、視覚障害者に限らないけど、障害者のための特別鑑賞会。開催期間中に1日だけありますよね。
林 昔からやってますもんね。
佐藤 それに気がついたときとか、音声ガイドのあるところとか。現代美術のインスタレーションは体験型で間口が広くて行きやすいですね。だから、いろんな美術館に行くっていう感じにはならなかったですね。昔は1人で美術館に行ってぼーっとしてたりもしたんですけど。美術館や博物館ってその中にいるだけでも気分がいいじゃないですか。あの美術館の雰囲気が好きでね。
林 どういう空気が好きなんですか?
佐藤 なんだろうな…例えば上野の西洋美術館とかね。常設展をみたり、中を歩いたり。廊下でちょっと座っているっていうのもいい気分でしたね。
林 それは、独特の広さとか、静けさとかですか?
佐藤 だと思いますね。そういうのがなんだか落ち着いて居場所を得た感じで。美術の作品っていうのは作者1人1人が世界を見つめて突き詰めていって出来てきたものだから、そういう精神的な世界の作品の集まりが作る空気なんじゃないですかね。あの新鮮な緊張感とか、わくわく感とか。
林 はい。
佐藤 何とも言えない充足感とか楽しさがありますね。人間が作ったものって非常に興味深いものだし。見えなくなってもね、それに触れたいという願望はあるんだと思います。
写真が持つ安定度と客観性と、余白
林 佐藤さんは東京都写真美術館のワークショップによく来て下さるイメージがあるんですが、写真はお好きなんですか?
佐藤 いや、全然写真にはなじみがなかったんですけどね。
林 そうですか。
佐藤 写真美術館では、水中写真家の中村征夫さんの写真は好きで行きましたね。ちょっと色もわかったから、ウミウシってこんなに色鮮やかなんだなとかね。あとは、岡本太郎展があったかな。東北のお祭りとか何気ない街並みとか、今ではそういう写真は資料にもなりますよね。で、その後にここのワークショップだったかな。見える人と見えない人で対話形式で写真を鑑賞していくと、絵でやるよりも情報が取り入れやすい感じがありました。
林 へえ、そうなんですか。
佐藤 絵画とかって見る人の思い入れがすごく激しいから。それがまたいいところなんでしょうけど、私は、絵画の場合は、そこに持たされてる意味をあんまり人を通したくないんですよね。
林 あぁ、それは、鑑賞者を介した形で絵画を感じたくない、と。
佐藤 そう、他の鑑賞者を通したくないっていうのがあるかなと思います。
林 なるほど。
佐藤 写真は、その人の感じているもの見ているものをそのまま情報として取り入れてイメージを作っていける、安定度が高い感じがして好きでしたね。
林 印象に残ってる写真ってありますか?
佐藤 今浮かぶのは、男の人の写真が3つ、若い時と壮年とちょっと年配になられた人のものがあって。それをずっと見ていて、少し後になってから「これは同じ人だね」ってわかったのを覚えています。
女の人のものもあって、それも年代が違う同じ人物なんですけど、若い時と20年以上経ってからで、髪型とか化粧とかが全部同じだったんですね。あんまり面白味がないっていえば面白味はないんだけど、「うん、こういう人いるな」って感じがすごくしたんですよね。
林 北島敬三の作品(※1)ですね。それを見て、その人の存在を感じたっていうことですか?
佐藤 そうですね。外見が変わらない人もいるし、変わっていく人もいるし。他にも双子を撮ったものもありましたよね(※2)。1人はピエロの恰好で1人は座禅みたいにして。
林 それはどの辺が面白かったですか。
佐藤 演出でずいぶん変わるなってことですかね。
林 双子を撮り続けている写真家だけど、双子といっても環境によっては別人のように見える人たちもいたりして。写真家の演出というか、見方がすごく反映された写真でしたね。
佐藤 あとは、軍艦島の写真。炭鉱から出てきたたくさんの炭鉱夫たちが、水を浴びて3つぐらいのお風呂に入っていく。要するに煤を落とすために。筋肉のある人たちで、その写真をみんなで見ているうちに、なんだか誇らしいね、とか、活気のある雰囲気を感じるねって話も出て、それも面白かったですね。
林 印象に残った作品は、人物の写真が多かったですね。
佐藤 そうですねぇ。私、人物に興味があるのかなぁ。

東京都写真美術館でのワークショップの様子
佐藤 視覚障害者の場合は写真ってなかなか見づらくて、わからないって思い込みが多いと思うんですよね。
林 どうして視覚障害者にとってわかりにくいんですかね?
佐藤 写真は目からの情報ですよね。ある程度、目を通しての情報が直接取りにくくなった人は、写真は離れるだろうなって思います。
林 でも何かのときに佐藤さんが写真は結構好きだっておっしゃっていた気がして。写真美術館の振り返りのときだったかな、写真が好きになった、みたいな言い方をされていて。
佐藤 そうだったかもしれないですね。切り取り方がすごくシャープでいいですよね。それから記録性もあるし。写真撮影にはまっている友人がいるけど、その気持ちもわかる気がしますね。被写体に対しても欲が出てくるだろうし。
林 何にはまるんですかね?
佐藤 何なんですかね、その場面を切り取りたいって思うんですかね。例えば、猫が走ってたとして、その猫の影のところがパパッと目に入って、その瞬間を残したいっていう。もっと他にもあるんでしょうけども、そのあたりは私もわかる気がします。
林 それは記録性ですよね。猫がそこにいたことを留められるという。
佐藤 そうですね。走った猫の後ろにあったあの影、とか、光の時間単位の加減や角度、季節とかで木の葉っぱがすごくキラキラする瞬間とかね。それを自分のカメラに収めたい、そういうところに私の友人ははまったのかな。
林 本当は止められないけど、写真ならできるから。
佐藤 うん、そういうものを求めて、写真にはまっていくんじゃないですかね。
林 確かに、その記録性は写真の大きな力ですよね。でも、佐藤さんが写真を見て楽しんでいるのはそこだけではないですよね?さっきの写真も、炭鉱夫を記号的に受け取っているわけではなくて、みんなで話していくうちに、そこに生活とか歴史とかプライドとか映りにくいものが見えてきたっていうところですかね…?佐藤さんは、写真の何を楽しんでいるんですか?
佐藤 何だろうな…。写真という動かない画像があって、それを前にしてみんなで一緒に鑑賞して分かち合っていく、っていうのは、次々と気が付くまま感じるままに言葉を出しやすいんじゃないでしょうか。情報交換がすごく豊富な気がします。絵画だと「これを言うのは的外れかな?」とかいろいろ思うのかもしれませんね。写真の方が、材料としても安定度が高いっていうか。それぞれの言葉、印象、いろんなことを情報として取り入れやすいと感じます。
林 客観性、ですかね。でもその客観性の土台から、炭鉱夫たちの生活感とか全然違うものも見えてくるってこと…ですかね?
佐藤 いつ頃の写真だろうねっていう話も、一つのポイントでしたよね。軍艦島が石炭の場所で、日本中がまだ石炭に支えられて発展してた頃っていう時代背景。写真だとそういう推測もできるんだなって思うし。
林 はい。でも…例えばさっきの、同じ人物を時間を隔てて撮ったポートレートは、客観性というよりもその人物の存在感というか、客観性とは別のものを楽しんでいたような気がするんです。
佐藤 そうですね…その人の個人的な生活がちょっと見えるような感じでしたよね。
林 客観的な、証明写真みたいな写真でしたよね。無表情で。
佐藤 女の人のはそうでしたね。だから職場環境もあんまり変わらなかったのかなって感じがしたかな。
林 そうか…。写真って言ってもいろいろありますよね。
佐藤 そうでしょうね。例えば、風景の写真だっていろいろで、風景なんだけど抽象的な作品っていうのもありますよね。
ある写真のこと
林 風景といえば、震災後の風景写真(※3)をみんなで見ていたときのことで、よく覚えていることがあるんです。
陸前高田の、津波でさらわれてしまって何にもなくなったような海辺の写真を撮っていて、明け方の時間なのかな、すごく光は綺麗で、残された木がポツンと立っている。そんな写真を見ているときに、たぶん震災から数年のタイミングだったと思うんですけど、ある参加者の方が「頑張っていこうっていうシンボルに見える」っていう、割とはっきりしたメッセージを受け止めていらしたんですね。
でも、佐藤さんは「いや、私にはそう見えない」ってはっきり言っていて。「そういうメッセージじゃなくって、もっと何か、太陽が毎日昇るっていうことをただ映してるんじゃないか」、つまりメッセージはないんじゃないかとおっしゃっていて。佐藤さんがそれを覚えてるかどうかわからないですけど…。
佐藤 覚えてます。いや、その写真は思い出せないんですけど、そのときに思い浮かんだことが私の中に蘇りました。
ある男の方のインタビューでね。震災の後、何が起こったのかわからないままに水が来て屋根に登ったんですね。どんどん流されていって。それで少し夜が明けて白々してきたときに周りを見たら、たくさんの家の屋根があって、そして、正面の海から、昨日と何も変わらない太陽がぐわあっと上がってきて。それを見たときにね、「全てがわかったような気がした」って言われてたんですよ。世の中の仕組みというか全てがそういうことだったんだっていう思いがしたって。この場面を思い出したんですよね。
林 その写真を見ていたときのこと、私はすごく印象に残ってるんですよ。情報量も少ないし、何もない海辺の風景をすごく抽象的に撮っている、客観性という手がかりがないタイプの写真だと思うんですけど、それなのに、一緒に見てた方は復興のシンボルをそこに見いだして、佐藤さんは真逆のことを見いだしていて。佐藤さんは何をこの写真に見ているんだろうって思っていたんですが、そのお話と写真がつながったっていうことなんですね。
佐藤 そこにいる人々に起きたこととは別に、変わらない1日が刻まれていくっていう、1日1日の姿。そういうふうに思ったんだと思いますね。
林 あの写真って結構よくわからない写真だと思うんですけど。
佐藤 ああ、そうでしょうね。写真だけ見ても。
林 ぼんやりしているし、新聞記事には絶対使われない、ワイドショーにも出てこないであろう写真。でも、屋根に登った男性が見た朝日って、そういう簡単な意味にはまとめられない朝日だったんだろうと思うんです。
佐藤 そうですよね。
林 だから写真って、意味でまとめないこともできるのかなとも思って。
写真美術館で展示されてるものって、そういった、余白の多い写真が多いと思うんですね。それを佐藤さんが楽しんでくれてるのかなと思って。
佐藤 あぁ、そうですね。写真って面白いなと思ったのはそれだと思います。
わからないことが好奇心を新鮮にする
佐藤 今、余白っておっしゃったけれども、私は、わからないっていう余白は非常に大事だと思うんですね。
林 余白、大事ですよね。
佐藤 有名な絵描きさんの展覧会に行くと、勉強もさせてくれるわけだけれども、何十点かある作品を見て、全ての絵がよくわかったって言う人がいたら、それは相当の能天気なわけですよ。この絵描きが好きっていう人でも、展覧会で好きだなって思う絵は2点か3点。それで、やっぱりわからなかったってものも私は必ずあると思うんです。
林 はい。
佐藤 美術展に限らず、例えば小説だって読み方は人それぞれだし、芸術作品でも仏像でも何でも、そこに何を見出すか、何を受け取るかっていうのは、人それぞれですよ。わかるっていうことも本当に人それぞれ。わかるって言う人もいれば、わかんないなっていう思いが強い人もいて。でもわからないからこそ、見に行くんですよね。わからないからこそ、見続ける。そういうことなんじゃないかな。
林 はい、はい。
佐藤 だから、わかんないってすごく意味のある大事なことだし、自分がわからないなっていうのを自覚してることが、好奇心を新鮮に持ち続けられるってことだし、それが、明日も1日生きてみましょうっていう(笑)
林 ふふふ(笑)そうですよね。
佐藤 ええ。そういうことですよね。
林 私はそういう”わからないことへの入口”を増やしていきたいと思っているんですけど、でも、たまに、特に視覚障害の人とかに対して「わかるようにこちらで全部用意しましたよ。わからないことは一つもないですよ」みたいな、”わからないことへの入口”を塞がれてしまうようなことってないですか?
佐藤 うん、そうなんですよね。私はね、わかるわからないは個人のことであって、第三者がそれに干渉することではないって思ってるんです。もちろん、なんらかの鑑賞のサポートは必要なんですよ、だけど、それで何がわかるかわからないかは、それはもう干渉することではないと思うわけですよ。余計なお世話っていうかね。
林 はい。
佐藤 作品でも人間でも、わかった気になるっていうのは危険なことでね。わからないことへの入口を塞ぐっていうそのやり方は、視覚障害者とか鑑賞する相手に「これとこれがこういうふうにわかればマル」って押し付けるような考え方ですよね。相手はそれぞれ別の中身がある人間だっていうことを無視して、自分を物差しにして相手に当てて。それは不愉快なことですよ。
林 不安なんですかね…例えば、美術館の側の人からしたら、来てくれた視覚障害者の人がわかんないって言って帰ったら不安になっちゃうんですかね。
佐藤 わかんないって思って帰るのは当たり前じゃないですか。
林 ですよねぇ。
佐藤 ある作品には感情移入ができたと思ったり、これはなんとなくわかったかな?ってクエスチョンマークだったり、結局わかんなかったなって作品もあったりして、それぞれの人が、そういうのをないまぜで抱えて帰るっていうのが当たり前だと思うんですよね。
林 そうですよね。私達の活動も、見えることと見えないことわからないことを言葉にしましょうって言い方をして、「みんなと一緒にわからないところに行きましょう」と、やっているつもりなので、ああ、それでいいんだって、お話を聞いてすごく心強く思いました。
佐藤さんにとって、芸術に触れることの満足感は、わからないっていうところにアクセスできることですか?
佐藤 そうですね。わからないから好奇心が新鮮であり続けられる。そういうのを誘ってくれるのが、美術展や芸術作品です。知的好奇心の根っこがあって、枝葉があって、その新鮮さを保ててる間は、アンテナに引っかかるものは読み続けるし、美術展にも行き続けるんじゃないんでしょうかね。

視覚障害者が登場する映画について語り合うワークショップ(※4)の様子 佐藤さん(右)と林(中央)
注1)2017年、東京都写真美術館「コミュニケーションと孤独」展でのワークショップで鑑賞した北島敬三《PORTRAITS》シリーズ
注2)2019年、東京都写真美術館「日本の新進作家vol.16 至近距離の宇宙」展でのワークショップで鑑賞した藤安淳《empathize》シリーズ
注3)2017年、ヨコハマトリエンナーレ2017でのワークショップで鑑賞した畠山直哉《陸前高田》シリーズ
注4)2024年自主企画、「目の見える人、見えない人が映画・ドラマ体験を語り合うワークショップ ~『座頭市』から『恋です! ~ヤンキー君と白杖ガール~』まで〜」
(編集 熊谷香菜子)