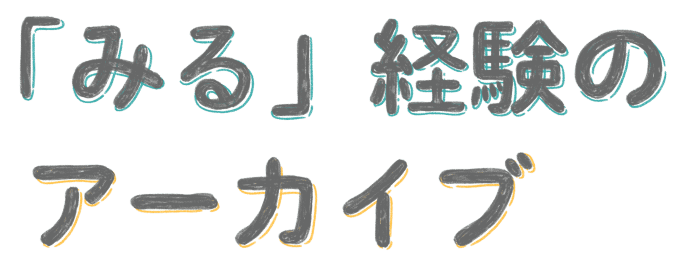「みる」経験のインタビュー Aさん

このインタビューは、目の見える人、見えない人、見えにくい人、さまざまな立場の人に「みる」経験をインタビューするシリーズです。
美術を鑑賞する方法には、目で見るだけではなく、目の見える人と見えない人が一緒に言葉を交わしながら「みる」方法や、触れながら「みる」方法もあります。それぞれの経験は、記憶や経験、他者の言葉など、環境との相互作用によって変化していきます。その変化のプロセスに目を向けて、さまざまな「みる」経験をインタビューとして記録します。
「作品の中に入っていく」。全盲のAさんは、美術館での鑑賞の体験をそう表現します。1人の説明だけでは作品を「外から見ているような感じ」でも、複数の人と鑑賞すると「中に自分が入っているような感じ」がしてくるというAさん。参加者の言葉を手がかりに想像を膨らませたり、自分の発言が他者の解釈を広げたりすることで、相互に影響しあいながら展開していく鑑賞ワークショップ。その中で生まれる “みる経験” について伺いました。
プロフィール
Aさん(東京都内在住、在勤。全盲、女性 )
幼い頃から触る絵本や彫刻に直接手で触れるなど触覚を通しての作品鑑賞が大好きで、何時間も飽きずに楽しんでいた。「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」に参加したきっかけは、晴眼の友人と絵画鑑賞をしたこと。直接触れないものでも描写してもらいながら味わえることを実感し、その経験をさらに広げたい・深めたいと思った。
聞き手
林建太 (視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップスタッフ)
和田美佐子(視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップスタッフ)
渡邊果歩 (岩手大学大学院 総合科学研究科2年生)
作品の見方が変わっていく
林 普段、美術館には行かれますか。
A そんなにはいかないんですけれども、視覚障害者と一緒に鑑賞するようなワークショップや、触れるような展示があると、年に1回ほど行ったりします。回数的には多くないのですが、1回1回の鑑賞をとても密度濃く楽しんでいます。
林 Aさんに初めて私たちのワークショップにご参加いただいたのは、2022年に千葉市美術館で開催したワークショップですよね。
A そうですね。
林 『とある美術館の夏休み』というタイトルの展覧会だったんですけど、印象に残った作品はありますか。

とある美術館の夏休み展のチラシ
A あの時みんなで出し合った言葉やイメージを、美術館の方がワークショップに参加した人たちに送ってくださったんですけど、今回のインタビューに合わせて読み返してみたんです。コピー機で自分の顔を写している作品があったなとか思い出しました(*1)。
林 展示室でのワークショップ後に、皆さんの会話の中で出てきた言葉を大石将弘さんという演劇の俳優の方と振り返って、その言葉を大石さんが声に出して読んでくれたんですよね。なんだかすごく面白い体験でしたよね。
和田 面白そうですね。私は、実際そのワークショップの場には参加していなかったのですが、そのときの大石さんとの振り返りのテキストを、参加者の皆さんに送ったということですよね。
林 そうですね。そうやってバラバラの言葉を書き出してみると、脈絡があるようでない詩のようなテキストに出来上がって。それを大石さんが声に出して読み上げる「とある日の言葉を集める ワークショップ」という企画でした。Aさんのコメントも入っていましたよね。
A そうですね。一番最初に見た作品だと思うのですが、描かれているものの説明をしてもらって、私が「身の回りにあるようなものを並べて、片付けようとしているのかな」というようなことを言ったんです。でもそれは他の人にはなかった見方みたいで。そういう見方もあるということが、ちゃんと皆さんに受け止めてもらえたというか。見える人もそうだと思うんですけど、そこに参加している人たちが、本当に自由に感想を言ったりできる、そういう雰囲気がとってもいいなと思いました。
林 はい、僕も思い出してきました。
A 今こうやってお話して、そのときの感じを少し思い出したんですけど、このとき本当に楽しかったという印象が残っていて、全員で作品を囲んで話をしていくというのは想像していたんですけど、予想以上にそれが楽しかったんです。
林 具体的にはどんなところが面白かったですか。
A みんなで作品について言葉にしていくことで、その作品のそれぞれの見方が広がったり深まったりしていくのが、とても面白いと思いました。自分自身が発言したことを通して、周りの人の作品の見方が変わったり、周りの人の”見る”ということに対して、自分が何か貢献できるような感じが持てたのも良かったです。
林
そうですね、自分の言葉が誰かに届いて、予想外の波紋が生まれるというのは醍醐味ですよね。千葉市美術館の次にご参加いただいたのは、2023年の国立新美術館でのテート美術館展でしたが、印象に残っている出来事はありますか。
A そのときにどういう絵を見たか家に帰ってからメモしておいたんですけど、三つ目に見た作品で、「病院の廊下と、通路の奥にレントゲン写真のような紫の出入口があるような感じの写真を見た」とメモしてあって。一緒に見ていた目の見える人たちは、この紫の出入口の方には、なんだか行ってはいけない気がするっていうような話をしていたんですね。でも私はそのときに、病院を早く出るためにその出入口に早く行きたいと感じて、そう発言したんです。
その時はそう感じたんですけど、でも後から考えると、その紫の出入口ってやっぱりあまりないような感じかもしれないし、ちょっとそっちに行くのは危険なのかなって、今説明を見直すと思うんです。でも全員で鑑賞してたときには、そんな印象を持たなくて。そこに集まったメンバーと一緒に鑑賞してるときにしか持ってないっていうか、そのときだからこそ感じるような印象はあるのかなって思いますね。

テート美術館展にて《廊下》を鑑賞している様子
林 そうですね、キャサリン・ヤースの《廊下》という作品(*2)で、ライトボックスを使った作品なんですよね。病院や学校のような施設の廊下を写した写真が、何か不思議な光で光っていて。みんなはさらなる異世界への入口みたいな捉え方をしてる人が多かったんですけど、Aさんは、今いる場所からの出口なんじゃないかみたいな、そういうお話でしたね。
A そうやって異世界から現実に戻ってくるような出入口みたいな、そういう見方っていうのは、その場に一緒に参加して、説明を聞いたり自分も印象を話したりしているときじゃないと思っていなかったかも知れないですね。
林 そうですよね。確かにその場でみんなが不安がってる様子とか、ちょっと落ち着かない感じで、このときは話してたと思うんですけど、確かにそういう情報が加わらないと見えてこないものはありますよね。
A 病院とかレントゲンとかちょっと不安になるような場所の印象が強く伝わっていったのかもしれないですね。なので「早くそこから出たい」っていう思いを持ったのかな。
林 そのときは、Aさんはそれを映像的に頭に描いておられたんですか。
A あまり、映像で描いたりというのはなかったんですけど、廊下と言われて、どれぐらいの広さの廊下なのかなとか、廊下に何かものが置いてあったりするのかなとかが気になっていたような気がします。
林 そうか。では、何を構築していくと世界観のようなものが、Aさんとしては完成するんですか。
A どういう場所に自分がいるのかということが、自分もその中にいるような感じでイメージができれば、という感じはします。
林 なるほど、「居る」という感じが抱けるとイメージが完成に近づくんですね・・ Aさんは、あの時写真の中に居たという感覚だったんですね。
A そうですね、中にいた感じ。
林 だからこそ、出口なのでは?という解釈が生まれたのかも知れないですよね。同じ作品の中で、同じように見ていたりちょっと違う立ち位置で見ていたりすることが、起きていたんですね。
言葉をヒントに作品の中に入る
A ちょっと全然違うことを思い出したんですが、小さいときにテレビを見ていて、何かテレビの中に入ったら、その世界に入れるんじゃないかって思ったりしてました。
林 あぁ~。
A やっぱり作品鑑賞したりするときって、”外から見る” というよりもなんだか ”中に入る” みたいな。こういうイメージが、自分の中では大きいのかもしれないです。
林 テレビに入るということを考えていたのは、目が見えなくなられる前のことですか。
A 少しは見えたかもしれないですけど、良く見えてたわけじゃないんです。
林 そうなんですね。テレビとか映画は、四角いフレームの画面のこっち側とあっち側がはっきりしてますよね。
渡邊 今の”テレビの中に入り込む” みたいな感じはすごく面白いなと思いながら聞いてたんですけど、そのときに一緒に鑑賞してる人たちの存在は、テレビのなかに一緒に入っていくイメージなんですか。
A 一緒に鑑賞してる人は一緒には入らない感じがしますね。周りの人の言葉をヒントにしながら、どんどん自分の中に入っていくみたいな感じです。
林 それは美術ならではの体験だったのかなという気がしますね。
A そうですね、美術館でいろいろな人と一緒に見てるからこそ感じられるという気はします。いろいろな人が説明してくれたりするからこそ、その作品の中に自分も入っていけるというか、1人の人の説明だけだと、十分にイメージが広がらないというか、自分もその作品の中には入れないような気がします。
林 その違いは何なのでしょう。大勢の方が説明する方がより正確さが増して、入り込めるぐらいのイメージになるという感じですか。
A 説明の正確さというよりも、いろいろな見方があるからなのかなという気がします。大学生のときに友達に説明してもらって一緒に作品を見たことがあるんですけど、1人の人に説明してもらうと、やはり外から絵を鑑賞してるような感じがするんですね。でも複数の人に説明してもらって、自分もその感想を言ったりしていくと、中に実際に自分が入ってるような感じになれる気がします。
林 それは、何でなんだろう。
A いろいろな人が様々な角度で話してくれて、そのイメージが膨らむというのがまず1つあると思うんですけど、もう1つには1人の人が自分の横で一生懸命説明してくれると、何かその説明を自分もしっかり聞こうって思って。
林 はい。
A いろいろな角度から発言があって、別にしっかり聞いてないわけではないんですけど、なんて言うんでしょうね、きっと誰かが発言してるのを聞くということだけに集中するだけではなくて、自由にいろいろ想像できたりもする、そんな気がします。
和田 傍観者になれるというような感じですかね。
A 確かにそんな感じがしますね。
和田 説明が自分に向けられているわけではないから、みんなの対話で空間とかイメージが立ち上がって、自分はそのどこにいてもいいというような自由さなのかなって、今聞いて思いました。
A うん、確かに自由さはあるような感じがして、それぞれのイメージでいいんだなと思えるというか。それだから一緒に周りの人と鑑賞できるということがすごくおもしろいし、いろいろな人と繋がっていけるような感じが、とても楽しいと思ってワークショップに参加してるんです。

テート美術館展にて《モレシュルロワン》を鑑賞している様子(出典:https://www.nact.jp/education/report/2023/0903_005312.html)
林 Aさんにお話を聞いてみたいなと思ってたことの一つが、今のお話にも繋がってくるんですけど、僕たちがやっているワークショップは、言葉を使うワークショップなので、発言の数で不平等が生まれないようにしたいなと、常々思ってるんですね。お話が上手な人とか、言葉数が多い人ばっかりが、活躍したり目立つ場ではないものにしたいと思っていて。実際そんなにお話されないけれど、すごく楽しそうにしてるなっていう人はいらっしゃってて、Aさんにもそういう感じをいつも感じていたのですが、Aさんの中ではどのようなことを感じられていますか。
A 作品の中に自分が入っていってるときは、やっぱりそのイメージが膨らんでたりとかして。でも思うんですけど、全く発言しないよりは、ちょっと自分の発言ができた方が楽しいかなとは思います。このワークショップでは、発言をするタイミングをうまく作ってもらえたりするので、発言できていいなと思って。
林 Aさんにとって鑑賞をするときには、一緒に見る人というかな、視点が複数あるということが大事なんですかね。 情報の量とか角度という意味でも、複数性が作用してるし、心理的に安心できるっていうことは、傍観者でもいられるし、意見を言う機会も必ず用意されてるっていうことですよね。
A そうですね。複数の視点があると、いろいろなイメージができて作品の中に入っていける、というのもあります。説明を聞くことだけに集中しすぎずに、鑑賞をただ楽しむこともできるし。作品を鑑賞するグループの一員としてそこにいられるというのも、ちょっと安心します。
林 うん。
A やっぱり複数で鑑賞するというのは、私にとってはとても大切な時間かなと思って。どっちかというと、心理的な安心感とかそっちの方が大きくて、ワークショップに参加してるのかなという感じです。
林 やっぱり見える側からすると、どうしても「説明しなきゃ」とか「情報の分量は適切か」みたいに目の前の人を“情報を与えるべき対象”としてだけ見てしまう瞬間があったりするんですよね。
A なにか、見える人にとっても、一対一で鑑賞していると「ちゃんと描写しなきゃ」「情報もちゃんと与えなきゃ」とか思っちゃうかもしれないんですけど、たくさんの人がいることによって、見える人もそういったプレッシャーとかが軽減されて、楽しく鑑賞できるんじゃないかなって、今ちょっと思いました。
林 確かにそうですね。なんかね、その役割の固定化から抜け出したいっていうのは常に思っているんですよね。他にAさんが話したいことって何かありますか。
A そうですね、ワークショップに参加したときのことをメモを見ながら自分で振り返っていたんですけど、さっきのレントゲンの写真の1個前に見た作品で、ヨーロッパの田舎街みたいなところで木とか草がたくさんあって、風が気持ちよさそうという絵があって。
林 はいはい。
A 鑑賞した当日や直後は、それほどその絵が印象には残っていなかったんですけど、今改めて振り返ると、その絵をもう1回鑑賞してみたいなと思っています。どんなだったのかなって。
林 はい、覚えてます。モレ・シュル・ロワンっていうフランスの観光地を描いた印象派の絵 (*3)で、派手ではないけど、すごく味わい深くて、お話も活発だったように覚えています。これをもう1回見てみたいと思う理由って何ですか。
A そうですね。もしそのときに多分どなたかが、木とか草があって、風が吹いてて気持ちよさそうみたいな描写をしてくれたんですけど、気持ちよさそうという印象が、なんだか私の中ではあまり残っていなくて。これが、どんな気持ちよさがあるのかなというのを、もう1回鑑賞してみたいなと思いました。
林 なるほど。言葉としては気持ち良さそうっていうのは聞いてたけど、もう少しそれを味わいたいっていう感じですか。
A そうですね、味わいたい。
林 これは逆に、あんまりこの作品の中には入れなかったということですか。
A 確かに、そうかもしれないですね。あんまり印象がそこまで具体的に残っていないので。
林 そっか、面白いですね。このときの僕の印象だと、他の参加者の人たちは結構、絵の中に入り込んで話していたんですよね。ものの描写とか筆のタッチがすごく印象的で、画家の身体の動きみたいな話がいっぱい出つつ、でもすごくいい季節で、風が吹いているとか、草の上で昼寝したい気持ちを誘うとか、その絵の中に入った話もたくさん出たんですよ。
A うん。
林 だから、もしかしたらAさん以外の人が中に行っちゃっていて・・
A かもしれない(笑)
林 というパターンもあるのかもしれないですね。だからその絵の中に入った話が出たからといって、中に行けるとは限らないから、なかなかこのメカニズムは面白そうですね。気持ちよさそうって言っても、気持ちよさそう感がそのまま伝わるわけじゃないってことですよね。
渡邊 絵を鑑賞してたときには、「気持ちよさそう」という言葉にピンと来ないこと自体は、気にならずに鑑賞していらしたんですか。
A うん、多分そのことが気になってたら、もっと頭に残っていたかもしれないですけど、特に気にはならなかったんだと思います。
渡邊 なるほど。私は結構、周りの人が入り込んでいる中で、自分はちょっとわからなかったら、焦っちゃったりするんですけど、でもわからなかったり、あまりピンとこなくても気にしないというマインドが持てることも、そういうふうに楽しめる雰囲気もまた大事なんじゃないかなと思いました。
林 だから、言葉にピンと来たからとか、没入できたから成功とか、そういうわけでもないのかも知れないですよね。
A そうですね。
林 何か結論めいたことは出せないけれど、なんだかすごく考えていきたいなと思うことですね。今日はどうもありがとうございました。
*1 井口直人《COPY》2015‒2022年
*2 キャサリン・ヤース《廊下》1994年
*3 アルマン・ギヨマン《モレシュルロワン》1902年
(編集 森尾さゆり)