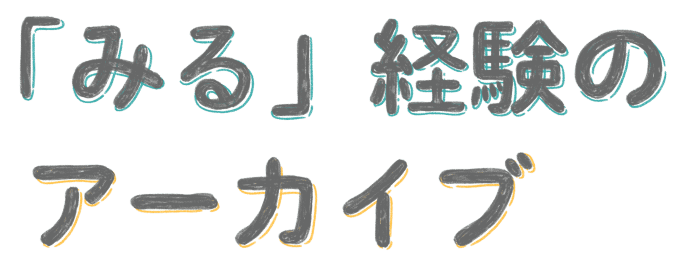「みる」場づくりのインタビュー [後編]亀井幸子さん(元美術館職員)

私たちは普段、目の見える人、見えない人、見えにくい人が言葉を交わしながら美術鑑賞する場をつくっています。
私たちの他にも、全国にはさまざまな立場の人と美術鑑賞をする取組があります。
そしてそこには必ず場づくりを担う人たちがいます。
さまざまな立場の人が安心して「みる」経験をするためには、どんなことを考えどのようにその場をつくってきたのか、その担い手にお話を伺い、「みる」場づくりのインタビューとして紹介します。
徳島県立近代美術館には、障害当事者の方も参加する「アートイベントサポーター」というボランティア組織があります。ここには、障害の有無に関わらず、そこに集まった人々と対話を重ねて一緒に作りあげていく「場」が存在します。組織の立ち上げから関わってこられた亀井幸子さんに、どのようにして場をつくってきたのか、ご自身の経験を交えながら語っていただきました。
プロフィール
亀井幸子さん
徳島県出身。徳島県立近代美術館で、エデュケーターとしてユニバーサル事業やアートイベントサポーターの立ち上げに携わってきた。美術館退職後の現在も、徳島とスリランカに拠点を持ち活動を続けている。
聞き手
林建太
視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップスタッフ。1973年東京生まれ。2012年から活動開始。鑑賞ワークショップの場づくりについては複数のスタッフと対話しながら試行錯誤している。安全な場をつくる方法には正解がないので他の実践者のお話にとても興味がある。
信頼して任せきる
亀井 見えない方も交えて鑑賞会をするときに触図があると話が進むので、同じ作品で触図を複数枚、手分けして作っていたんです。最初は1枚だけだったのを、順番待ちしなくていいように枚数を増やして。
それであるとき、3人のサポーターの方と触図を作ろうとしたら、みんなの意見が分かれてしまって、「じゃあ、1枚の絵で3人にそれぞれ作ってもらいましょうかー?」っていうことがあって。
林 1つの絵から、異なる3つの触図を作ったってことですね。
亀井 そうです。3人の方がそれぞれで作って、それが面白かったって言われました。
この人はここを伝えたかったのね、この人のは触るとカサカサ音がするのはこういうことが気になったのね、って、触って違いをわかることができてイメージが広がって、答えは一つじゃない、いろんな見方や感じ方があっていいんだ!っていうのが触ることでも実感できたんだと思います。
林 「1つの絵に対して1つの触図を作りましょう」っていう当初の目的を、「いや、3つにしましょう」って、柔軟に変えられるというのは…それを変えるのは誰なんですか?
亀井 作品の技法や構図、構成とかがあるので、私が最初の話題提供をある程度します。風景画だったら前景・中景・遠景をわかって欲しいなという話をすると、サポーターの人たちが「じゃあ、手前のものと、奥のものとで、どうしたらできるだろう」みたいな話し合いをしてくれるっていう感じですね。
林 あぁ、じゃあ、3つにしましょうって亀井さんが決めたわけじゃなくって…。
亀井 この時は本当に意見がまとまらなかったんです。対話鑑賞をすごく重ねたので、3人のサポーターの方の大事にしたいことが一致しなかったんですよね。「じゃあもう、どうせ複数枚必要なんだし、それぞれで作ってみます?」みたいなことでした。その行き当たりばったり感がプラスに働いているのかもしれないですね。
振り返って考えてみると、唯一自分が大事にしていたのは、サポーターの思いを尊重することです。サポーターの方が「亀井に言われたからしたんだ」じゃなくて、「私がしてみたかったことを、亀井がいいねって言ってくれたのでやってみたら、楽しかった」となるように。だから、サポーターの方が「こんなのはどう?」と言えば、私は「それいいかも!」、また次に「いや、こういうふうにしたら?」と言えば、私はまた「それもいいかも!」って、ニコニコしながらサポーターのみなさんの意見についていった。私は風見鶏みたいでしたけど、大事なのはサポーターの思いだから、それでいいって思っていました。
林 なるほど。
亀井 自分の要望をあんまり表立って出さないようにというのも、途中から意識しだしたと思います。当事者の方たちの意見って、自分では思いもよらないようなアイディアだったりするので。なので、あんまりかっこよく言えないですけど、信頼するとかですかね。
ワークショップを企画しても、あんまり深く考えず。来てくれた人がいて、サポーターがいてくれたら何とかなると思ってずっとやってきて、実際そうでした。信頼できるメンバーに出会えているので、自分が大事にすることは、信頼すること、任せきること。ちょっと難しいですけど、ちょっと不安もないことはないんですけど、やっぱり任せきる。それで何かやりがいを感じてもらうことを一番大事にしたかったですね。
林 そうかぁ。
亀井 普段はこんなに考えてないです、やってたら楽しいので(笑)

実施中のワークショップの様子を遠くから眺める亀井さんの写真(左)
ポジティブにルールを変えていく
林 ろう者のイベントサポーターの方が考えた、聞こえない人も聞こえる人も参加できる「筆談トーク」っていうプログラムがありますよね。だけど、「見えない私達も参加したい」って、別のイベントサポーターの方がそこに合流していくという話を聞いて。「そっか、そこのルールも変えていいんだ」って、すごく面白いなと思ったんですよ。
亀井 でもね、ここだけの話で、私、見えない方が参加できないワークショップもありだろうなって思ってたんです。
林 ええ、そう思います。しょうがないというかね。
亀井 この筆談トークは、音声言語もダメ、手話もダメ、ひたすら筆談。ちょっと笑ったりっていう声はいいけど基本サイレントで、紙の上のコメントだけが積み重なっていくものです。なので、そこに話し言葉はダメだろうなと思って、実は、目の見えないサポーターから言われた1年目は、そのご意見をスルーしちゃったんですよ。
林 そうなんだ。
亀井 でも次の年、「やっぱりすごい楽しそうだし、どんなものか自分たちも体験したい!」って仰って。わー、どうしようか、困ったな、と思ったら、サポーターの方々が「やってみましょうよ」って言い出してて。それは無理ですよってとても言える空気ではなくって。どうなるんだろうと思いながら、あの手この手で何度かトライアルをして、本番でもやってみたっていう感じで。
林 結果、目の見えない人はしゃべっていいことになったんでしたっけ?
亀井 最新のものではそうですね。ワークショップでは、展示室の作品の近くに机を持ち込んで、そこに模造紙を置いて、作品を見ながら書き込むんです。一番最初は、やっぱり展示室の中で話し声が聞こえると気が散るだろうってことで、ロビーにも同じように机を置いて、模造紙と絵を描いたものと触図を用意しました。そこに見えない方とヘルパーさん、サポーター、一般参加の方にいていただいて。
ロビーで「これなんだろう、人かな?」と質問が出たら、ヘルパーさんが付箋に書いて、それを展示室に持っていて、筆談をしている人たちの中に貼ることで、目の見えない人から質問が出たことを静かに伝えてもらいました。そのコメントに対して感想とかの書き込みが追加されたら、サポーターが展示室でそーっとマイクを使ってコソコソと音声で読み上げてくれるのを、ロビーで聞くんです。
ラジオの手紙を聞いてるみたいに、読まれる音声にみんなで聞き耳を立てて、喜ぶ、みたいな。なので、そういう面白さはあったんですけど、これは筆談鑑賞の楽しさとは違うんですよね。距離もあったし、もう別個の鑑賞という感じで。
林 でも、極力話し言葉から距離を取って落ち着いた時間の中で進んでいくっていう、筆談トークの本質は失われてない気がするんです。それでも変わっていくっていうのは面白いですよね。
亀井 はい。だけど次の年のミーティングで「でも、やっぱりあんなに離れているのはおかしい」って(笑)
林 ははは(笑)
亀井 見えないけど、展示室の中の雰囲気とか、パサパサって書いてクスッて笑うみたいな気配を感じながら、自分たちも近くでやる方がいいんだろう、ということになって。
その次の年には、見えない方の机も展示室の中に入れて、見えない人がいるグループはしゃべってもいいことにして、しゃべったことをヘルパーさんやサポーターが書き込みました。途中からは、発案者の方の考えで、違う机に行ったりしてもいいことになって、どんどん書き込みがぐちゃぐちゃになっていって。それでも、机ごとにストーリーの動きが全然違うので、すごい面白かったですね。
それでも、このやり方で筆談トークの楽しさが伝わっているかというと、まだまだ進行形だろうと思います。対話鑑賞は言葉が消えていきますけど、筆談トークでは確実に文字として残って、言葉が積み重なっていく。なので、文字が読めれば話の展開がわかる、対話鑑賞とは違う面白さがあります。それを目が見えない方と楽しむには試行錯誤が必要だろうと思います。
私もどうなるのか全然イメージは湧かないんですが、目の見えない人も一緒に筆談鑑賞をやろうとすることで、みんながああだこうだ言って、いろんなアイディアが出てきて、トライアルをする中で、もしかしたら違うプログラムになっていくのかもしれないんですけど、きっと、これからもいろんな面白いことが起こってくるんだろうなと思っています。
林 楽しみです。
亀井 最初は、「それは無理やし、どうやって断ろう、やっぱりできませんってどうやって言ったらいいんだろう」って真剣に思ってたら、話が違うところで進んでいて面白かったですね。「やることになってるー!!」みたいな(笑)
林 そう、それが、すごく面白いというか、すごく真っ当なルールのあり方だと感じるんです。人のためにルールが変わっていくことが自然に機能しているのが、すごいなと思います。
亀井 発案者も、プログラムを次に生かそうっていう発想があるので、いろんなアレンジをすごくポジティブに受け取っていて。だから実現したことでもあるし、そのあたり本当に皆さんすごく素敵だと思います。
林 ええ。そのクリエイティビティを発揮できるのは、徳島のあの場所があるからこそだと思うんですよね。
亀井 アートって、既成概念とか、それまでとは違う新しい価値を見いだしたり作り出したり、発見したりすることじゃないですか。
サポーターの方たちと「何、これ?」みたいなヘンテコな作品を見て、みんなで頭を抱えて、無言になる瞬間も、どう言っていいかわからないような思いも、みんなで共有していく中で、みんなでちょっとずつ成長してきたのかなって、今はそう思います。
本当にいい作品っていうのは本当に何言っても許される、ピカソの絵のことを「こんなの私でも描ける」って言ってもそれさえ許してくれるみたいな懐の深さがある、そういう本物の作品を介しての活動でしたね。アートという、すごく懐の深いものを介してだからこそできたこともあっただろうなって思います。
直接人と人だと難しいんですけど、不思議で不可解なアート作品を介しての活動なので、面白いことの方が多かったですよ。そういう意味では美術館でやる面白さっていうのは本当にあるんだろうなって思いました。
願いとこれからのこと
亀井 私自身もですけど、美術の教員は絵を描くのが好きなので、生徒もそうだろうと思い込んでいて、鑑賞の授業ってそんなにやらないんですよね。社会に出たら、絵を描く時間なんかなくて、旅行先の美術館で絵画とか見て楽しむ機会の方がずっと多いのに、鑑賞の楽しさを学校教育の場で学ぶ機会が少なくて、美術館が一部の美術ファンだけのものになってしまうという傾向があったように思います。でもそうじゃなくて、障害があってもなくても、いろんな人に美術館に来てほしいんですよね。
林 はい。
亀井 私が担任していた障害のある生徒達って、行けるところがすごく限られているんです。そういう意味では、美術館って比較的安全だし、空調が効いてて、でこぼこもないから、重い障害のある人たちでも安全に来られる場所になりうるんだろうなと思っていて。
重度の障害のある生徒たちは自分では来られないので、介護している方や保護者に「あー、美術館に連れて行ってもいいよな」って思ってもらえるような美術館にしたかったっていう思いは、根底にあったと思います。
ある研修現場で支援学校の先生が「私が連れて行かないと、生徒たちは一生美術館に行くことはないかもしれない」ってつぶやいてたんですよね。
ヨーロッパとかでは、芸術や文化を楽しむのは本当に基本的人権の一つで、生活保護を受けている人でもコンサート行ったり映画見たりして芸術を楽しむのは人間として当たり前。それが、日本ではなかなかそういう状況になくて、文化や芸術を楽しむことは後ろに回されている。
当事者の方も周りの人も、美術館よりもっと楽しい遊園地に行った方がいいとか、重要なのは病院のサポートだとかで、美術館に行くことの優先順位はずっと後ろだっていう意識があるとしたら、とても残念なことだし、何とかしたいって思います。
障害があっても、美術館に行って何かできる。見えないかもしれない、どこまで認識できるかはわからないけども連れて行く。そして、本物の絵の前に立って、暗い感じとか、シーンとした感じとか、人がいっぱい見に来てる感じとか、そういうのを一緒に感じる。障害があるから、わかんないから行かなくていいじゃなくて、美術館に行ってみようかなって思う人をちょっとずつ増やしたい。ユニバーサル事業って言うと硬くなるんですけど、いろんな人が来てくれる美術館にしたかった。なので、サポーターの方たちといろんな面白いワークショップを考えて、いろんな興味のある人とつながれたらいいなと思っていたんです。
林 ええ。
亀井 それともう一つ。最初、ユニバーサル事業を立ち上げたときに、視覚障害、聴覚障害、幼児、高齢者、外国人の5つの分野で同時進行したんですが、その中で、外国の方との活動が思うように進められなかったのが心残りで。
大学の留学生の方とはずっとワークショップをやってましたが、彼らは母国ではエリートだし、いつかは母国に帰っていく。地方の公立美術館として本当につながりたいのは、徳島に住んで仕事に就いている、本当に徳島で暮らす人たち。そういう方々に、美術館を遊びに行く場所の候補の一つにして欲しかったんですけど、現実にはそういう方々とつながることが難しくて。
定年後も再任用で美術館に残ってユニバーサル事業を続ける選択肢もあって、それはとても魅力に満ちて楽しいに違いなかったんですけど、でも、限界を感じたんですよね。せっかくならアンラーニングっていうか、今までの自分の常識をリセットして違うところから学びたい、そのためには、徳島から離れることかな?って思って。それで、息子が暮らしているスリランカに、表向きは息子の手伝いということで行くことにしました。
価値観、文化の違いにちょっとずつ出くわしています。やれることは何かありそうだし、あと数年は頑張って、スリランカで活動の拠点をいっぱいつくって、最終的には徳島とスリランカを半々ぐらいで行ったり来たりできたらいいなと思ってます。
林 なるほど。
亀井 スリランカでは、国が行うテストで良い点を取って無償の国立大学に入ってエリートを目指すため、あるいは海外で働ける語学力を身に着けるために、幼稚園ぐらいから英語を勉強させる家庭が増えているそうです。本来子ども時代に学び経験しないといけないことよりも、知識重視の早期教育が広がってきていることに危機感を持つ先生たちと出会うことができたので、アートによる教育で目指してきたことをちょっとずつでも伝えられたらいいなと思っています。
その前に、言葉が通じないんですけどね。でも、ノンバーバルの、言葉が通じなくても何とかなるよっていうワークショップをずっとやってましたから。スマホで最低限やり取りできたらいいんじゃないか、とにかく何かやりたいことがあって伝えたかったらいくらでも方法はあるので、そんな感じで活動をしていこうと思っています。
あと、日本語を学んでいる大人の方も多くて、そのお手伝いをしているんですが、ひたすら試験勉強ばかりなのが私は残念で。試験に受かることが最優先なので、彼らの切実なニーズとはかけ離れてるかもしれないんですけど、言葉が通じなくてもわかり合える楽しいワークショップとか、絵を見て感じたことをやさしい日本語で話し合えるようなオンライン鑑賞会みたいなものも提供したいと思っています。
林 最初、スリランカに行くって聞いたときは意外だったんですけど、亀井さんの中で自然なことだったんだなって思えてきました。
亀井 退職後どう生きるかって考えたときに、これが最後のチャレンジかなあって。出会いとか新たなネットワークでいろいろつながっていくのはすごく面白いです。
私自身もそうだったように、地方にいると海外と接点を持つ機会って少ないから、徳島とスリランカの子どもたちで交流ができれば、双方にとってもプラスになるだろうと思って、将来的にはそんなことも考えています。
林 今日は亀井さん個人の話が聞けてすごく良かったです。ありがとうございました。
亀井 質問されて初めて考えてることがいっぱいあって、普段いかに考えないか…。でもあんまり考えると心配事が増えちゃうので、やってみて後からちょっと反省をして、また次、やりたいことをやっていくのが私なりの継続なのかなって思っています。
美術館では素敵な仲間に恵まれ、本当に楽しく仕事をさせていただきました
。これからも美術館とか社会教育で役に立てることがあったら精一杯頑張りたいなと思ってます。こちらこそ貴重な機会をいただきありがとうございました。

関連資料
徳島県立近代美術館 ユニバーサルミュージアムのとりくみ
関連資料では、これまでの取り組みをまとめた冊子や紀要をPDFで読むことができます。
リンクはこちらから
(編集:熊谷香菜子)